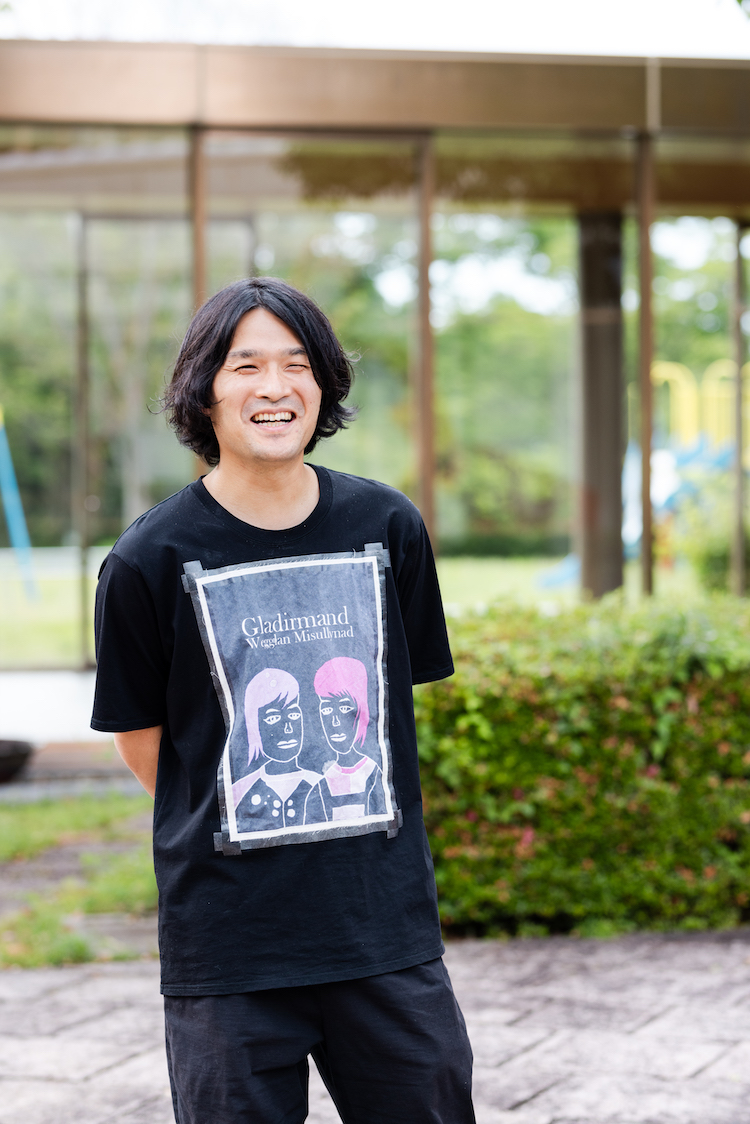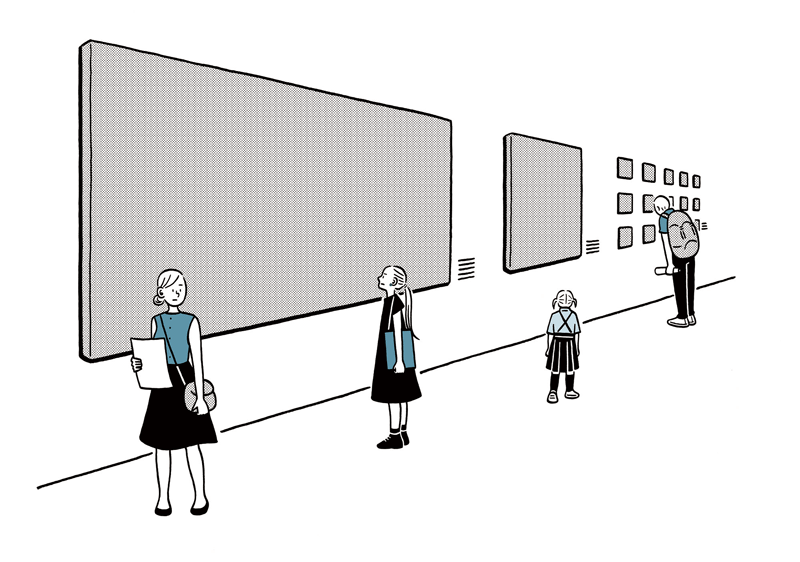「ジャポネ展」から「つくる冒険」にいたるまで
「つくる冒険 日本のアール・ブリュット45人」(以下、つくる冒険)は、2010年にパリで行われた「アール・ブリュット・ジャポネ」展(以下、ジャポネ展)の出品作が土台となっていると聞きました。まずは、そのあたりの経緯を教えてください。
「ジャポネ展」は、日本でアール・ブリュットという言葉が広まる大きなきっかけとなった展覧会でした。このときの出品作の大半を日本財団が収蔵、保管してきたのですが、昨年、これを当館へご寄贈いただきました。これは、ある面では日本におけるアール・ブリュットとは何かを形成した作品群でもありますので、それを整理しながらなるべく多くの作品をご披露するというのが、この「つくる冒険」の大きなミッションのひとつでした。ただ「ジャポネ展」の展示構成をなぞるのではなく、開催からおよそ15年の月日が経っていることも意識して、今の視点から展示を再構成して、新たに5つの文脈で組み上げていきました。
5つの章タイトルは想像力が膨らむような言葉になっていますが、「ジャポネ展」との大きな違いはどこになるでしょう。
第4章「社会の密林へ」、第5章「心の最果てへ」と題した展示の後半部に、その違いを表す意味を込めています。デュビュッフェによるアール・ブリュットのアイデアは、彼が精神科病院で見た精神障害者のつくるものに大きな影響を受けて提唱されたものです。ですので、当時の精神医療の状況とも重なるのでしょうが、これまでアール・ブリュットといえば、秘密、孤独、沈黙という言葉とともに語られてもきました。一方で、日本から紹介された作品は、福祉の現場で支援を受けた知的障害のある人たちの創作活動から出てきたものが多く、秘密、孤独、沈黙という形容とズレを感じるものが少なくありません。そのことをあえて主題化するかたちで、第4章「社会の密林へ」では、社会との交わりを感じさせる作品を集めました。
逆に欧米の方が見たら、「これもアール・ブリュットなのか」と感じるかもしれない作品群ということですか?
そうかもしれません。日本におけるアール・ブリュット受容に誤解があることはよく指摘されます。概念の厳密さを守ることも大切ですが、その一方で、もともと定義された概念とは違う性質を持ったものが、今日、アール・ブリュットという言葉で呼ばれていることについて検証することも重要であると考えています。
第5章の「心の最果てへ」で紹介しているつくり手のなかにには、精神疾患を発症した人たちも少なからず含まれています。精神疾患は、アール・ブリュットと深い結びつきをもったトピックともいえます。これまでも、アール・ブリュットの展示のなかでは、精神科病院での長期入院という孤立的な環境下で書き殴ったようなノートブックが、ある種、人間の原初の衝動的なものとして紹介されることもありました。
ただ、現在の倫理感覚では長期入院のような孤立的環境などに起因する表現を単純に称賛するのは難しく、当時の社会的要因が描かせたものであることも忘れてはならないことだと思います。もちろん、魅力的な作品群であることは否定しませんが、ちょっと立ち止まって考える時間も持ってもらいたい、というのが「心の最果てへ」という章を組み立てるにあたって私が考えていたことです。
展示作品と問題提起は別レイヤーで
広報物のデザインをはじめ展覧会全体のイメージはポップで明るいものになっていますし、今、おっしゃったような議論が作品キャプションなどに明示されているわけでもありません。そうした問題意識や情報をどのように伝えられているのでしょう。
展覧会タイトル自体「つくる冒険」ですから、ワクワクした雰囲気の展示にはしたくて、例えば「アール・ブリュット~衝動の芸術」みたいな重厚な感じは避けるよう、デザイナーとも何度も打ち合わせました。その上で、個々の作品はとてもすばらしいものですから、まずはそのことを感じ取っていただきたいと考えていました。アール・ブリュットをめぐっては、さまざまに議論がありますし、今回の作品群からもさまざまなことを語ることができますが、問題提起のための材料として彼らの作品を使ってはいけないとも感じています。ですので、そうした議論や問題提起は図録内のテキストやギャラリートークといった、関心を持って一歩踏み込んだ方が触れることのできる場面で発信するようにしています。
では、「つくる冒険」というタイトルにはどういった意味を込めましたか。
単純に、冒険=ドキドキワクワクのアドベンチャーというわけでもなくて、もう少し抽象的な繊細な感覚のある冒険として考えています。たとえば、日常生活で見つけたものをセロハンテープでくっつけてみたら、それだけで何か見たことのないかたちが生まれた……それはとてもすてきなことですけど、一方で、それによって彼らは、何年もの間、その行為をし続けることを選択したのかもしれない。そうしたちょっとスリリングな営みでもあることも含んだタイトルとして、「つくる冒険」という言葉を選びました。

NO-MAから滋賀県立美術館へ
山田さんは、近江八幡の「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」(以下、NO-MA)から2022年に滋賀県立美術館へ移ってこられました。社会福祉法人グローが運営するNO-MAは、アール・ブリュットについても日本で先進的に取り組んできたミュージアムですし、グローの前身となる滋賀県社会福祉事業団が「ジャポネ展」の出展者をとりまとめたという経緯もあります。NO-MAから美術館へと移って、違いを感じていることはありますか。
とても単純な答えになりますけど、規模の違いを一番に感じます。展示企画やワークショップにしても、美術館だとやっぱり段違いに反響が大きくて、波及効果の高さを感じているところです。「つくる冒険」の前に、昨年は「“みかた”の多い美術館展 さわる知る 読む聞くあそぶ はなしあう 「うーん」と悩む 自分でつくる!」(以下、みかた展)という展覧会を担当したのですが、これもNO-MA在籍の頃からチャレンジしてきた、いろんな立場の人たちにミュージアムへアクセスする回路をつくるべく企画したものですから、自分のやっていることは変わっていないと思うのですが。
どんな企画だったのでしょう。
NO-MAでは2021年に「79億の他人ーこの星に住む、すべての『わたし』へ」という展覧会を企画して、知的障害、盲ろうの人たちも一緒に美術鑑賞を楽しむためにはどうすればいいか、当事者たちと会議をしながらそのための方法を考えるプロジェクトも並走させました。たとえば、盲ろうの人たちが作品を触りながらしゃべっていたことを記録して、その記録もあわせて展示したり、だとか。2023年の「みかた展」では、障害者だけでなく、外国のルーツを持つ子どもたちなどにも美術館へ来てもらって、どんな方法であれば美術館にアクセスしやすいかを聞き取ったうえで、なるべくそれを実現するかたちで展覧会を行いました。
マニュアルでは対応できないことがある
当事者を交えながらやり方を模索して、それをすぐに実装してみるということを、展覧会の機会にやってみたわけですね。
そうですね。アール・ブリュットや障害のある人たちの作品を展示する試みは数々やってきましたけど、それを誰にでも見てもらえるようにする「アクセシビリティ」については、まだまだ考えが足りてなかったのではないかという自分の問題意識がありました。実際にそういう試みをしていくなかで、アクセシビリティを解決する共通解なんてありえない、というか、ナンセンスだと気づきました。むしろ、個別のニーズに対応するための回路がないことが問題じゃないかと。
一律にこれをやっておけば大丈夫というものではないと。
施設のアクセシビリティを考える際に、マニュアルやメソッドを用意しすぎると、どうしてもそれに当てはめて対応してしまうので、実際のニーズとかけ離れることもあると思います。たとえば、スロープを設置して、展示解説には音声情報を準備してというのはごく一般的な対応ですけど、やっぱりそのマニュアルが通じないケースは結構多いですし、ひとつひとつのニーズを汲み取っていく柔軟さのほうが大事じゃないかな……ってうまくまとめましたけど、それはハードルが高くて簡単にできることではないのですが、ただ、基本的なスタンスとしてはそういうことを大事にしたいという思いは間違いなくありますね。
アール・ブリュットの展示と美術館のアクセシビリティのこと、通じる部分も多そうですね。この先、山田さんはどんなことをやっていきたいと考えていますか。
「つくる冒険」とその巡回展によって、これだけのアール・ブリュットのまとまったコレクションがあることを広く見ていただく機会がつくれましたので、これからは作品の貸し出しの話も増えてくるかなと期待しています。
一方で、「ジャポネ展」以降、日本でアール・ブリュットが受容されてからの展開についての話もしたいんです。ポスト「アール・ブリュット」と言うか、これまでのアール・ブリュットを相対化するような観点での展示を考えたいですし、また別の分野の作品と比較するようなかたちでの展示もやってみたいですね。決してアール・ブリュットという言葉を否定するわけではないですけど、今回「つくる冒険」で紹介した作品も、必ずしもこの言葉に縛りつけられる作品群でもないですから。

※近年の滋賀県立美術館の展覧会のチラシには、以下のような但し書きがある。「当館では、しーんと静かにする必要はなく、おしゃべりしながら、ご観覧いただけます。…(略)…ご来館にあたっての不安がある場合は、[お問い合わせ]からご連絡ください。事前の情報提供や当日のサポートのご希望に、可能な範囲で対応します」。