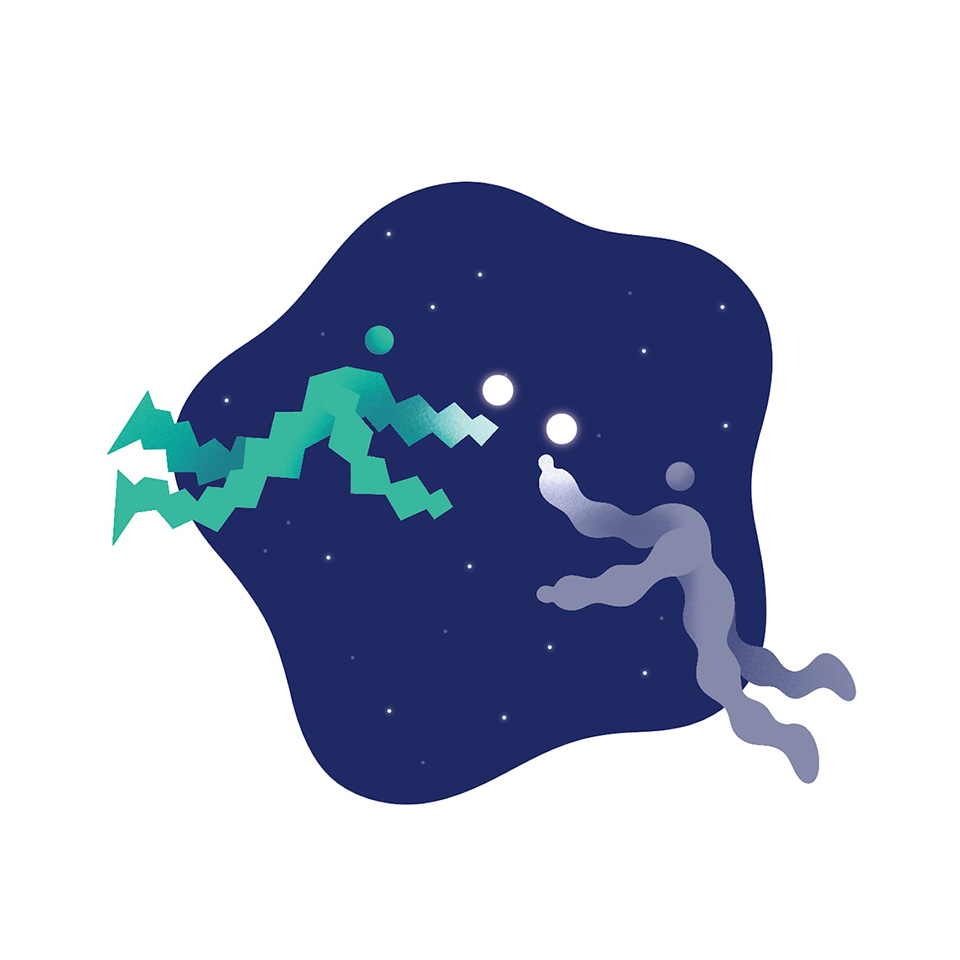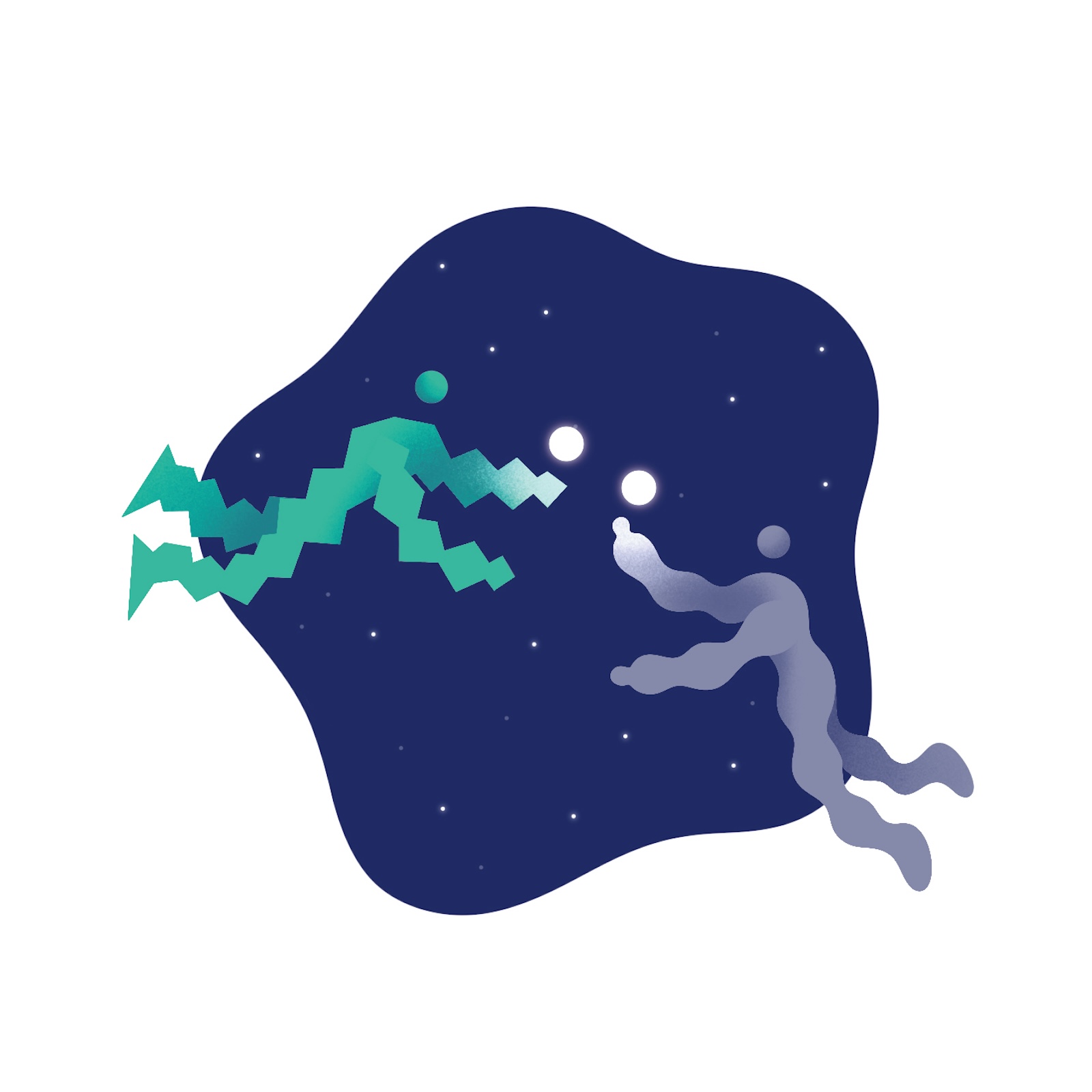*本記事は「子どもたちと考えた、よりよく生きるための物語——イタリア・ミラノの絵本出版社、カルトゥージアの実践」「ともに笑い、怒り、語るために 「わたしの幻聴幻覚」プロジェクト」「ともに語りなおすための術」の3記事とあわせてお読みください
人と出会ったとき、「この人と私は違う人なんだな」と反射的に感じることがある。たとえば、名前の異なり、使う言語、装いの選択、移動の方法やその速度の違い、疲れやすさ。しかし大抵、(通訳者や翻訳手段を伴い)話したり、何か飲んだり食べたりと時間を過ごすうち、この人と自分は似たような生活の課題や問題意識をもつのだと気づき、親しみ、先をゆく先輩のように感じることがあったりして、「違う」と感じた心身はほぐされていく。「違う」と心身が感じることは緊張でもあるし、知ることでもある。最初に「違い」を感じなかった、自分と同質的なはずの人と話すほどに「違い」を感じ、ゆがんだ笑いをつくって、この時間が早く終わってほしいと思うこともある。
偏見はどこまでも自分勝手だ。作品を通して、人と知り合い話すことは、傷つきと回復が常に裏表にある。協力者にとっても、そんな機会であったらいい。
ただし、作品制作の外にある「個人的な―親密圏」にいる人とも、そのようなやりとりはある。ということは、私は誰かから話を聞き、それを何らかの方法で記録し展示をすることによって「さまざまな人々による一時的かつ持続的な小さな共同体―親密圏」がともにつくられることを望んでいるのかもしれない。そして、そのために、すでにある共同体に寄留させてもらっているのかもしれない。
誰かの声を聞き、それを伝える方法とその言葉を選ぶことは、優しいようでいて、力そのもの、政治そのものでもある。
このような関係の共同体は、なんらかのマイノリティ性がある表現を社会に現すときに、その表現を複数の視点から検討し、万が一、外からの攻撃があったときに支え合える可能性をもっている。
異なる人々同士が集い話すためには、権利や尊厳をさまざまな方法で回復することが必要な場合もある。それにかかる時間は、その人の人生の時間だけでは済まないこともあるだろう。
それでも、それぞれの面白さとしんどさと面倒臭さを持ち寄り、聞き話し、またそれを誰かに話しなおすこと、あるいは話したモヤモヤを誰かに適切に注意されることによって、私たちは自分のなかにはそれまでになかった言葉や態度を知る。それはキラキラしていないかもしれない。私たちが身につけた身ぶりを一度捨て、学びなおす痛みを伴うかもしれない。けれども、そうした小さくて不可逆な、私自身を変えていく身ぶりの積み重ねが創造的でないわけがない。
それらの会話はきっと、誰のことも排除しない文化をこの社会に育む種だ。