※フリーペーパー『DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.15』は全国の配布協力施設・店舗にて入手いただけます。また本ページ末尾からもPDFのダウンロードが可能ですので、ガイドとなる本記事とあわせてお読みください
ステートメント
特集:おはなし 聞く、語る、語りなおすこと
目の前の一個の人間が自分には計り知れない存在である、という事実に行き当たるときに生じる「畏れ」は、その人の果てしなさと出会う「よろこび」と常に一対です。「聞く」ことを通じて、自分自身をつくりかえていく旅。
—小野和子『あいたくてききたくて旅にでる』(PUMPQUAKES、2019年) p.351 濱口竜介「聞くことが声をつくる」
民話採訪者として東北各地をめぐる小野和子さんの著書に、映画監督の濱口竜介さんがテキストを寄せている。そこでは「聞く」ことは、古い自分を打ち捨てて変革することだと記されている。「聞く」行為は、それに対する自身の反応に直面することと切り離すことができないのだ。小野さんの言葉を借りるなら「語り手に見合う自分をつくり出さなくちゃいけない」。
今号の特集は「おはなし 聞く、語る、語りなおすこと」。私たちを取り巻く社会、さまざまなコミュニティにおいて、これまで近くにあったにもかかわらず無いものとされてきた声、問われるまで本人さえも気づかなかった背景や見方、声を上げることすら抑圧されてきた語り。それらと、「聞く」ことを通して向き合い、ともに語りなおす術を探るために。各地の実践者と出会い、その語りを聞くことからはじめてみたい。
もくじ
REPORT|子どもたちの困難を生きるためのおはなしに変えるイタリア・ミラノの絵本出版社、カルトゥージアの実践

生きづらさを抱える子どもたちに寄り添い、声を聞き、絵本のかたちに昇華させる 、ユニークな出版社がイタリアにある 。ミラノに小さなオフィスを構えるカルトゥージア出版だ。小児がん、発達障害、親の離婚など、困難に直面する子どもたちが、問題に向き合い、壁を乗り越えていくことを助けるために、専門家の力を借りながらさまざまな「おはなし」を創作してきた 。その実践とは?
[文] 末澤寧史
[写真提供] 株式会社どく社
[取材協力] 多木陽介
[編集] 鈴木瑠理子(MUESUM)、多田智美(MUESUM)
INSIGHT|ともに語りなおすための術
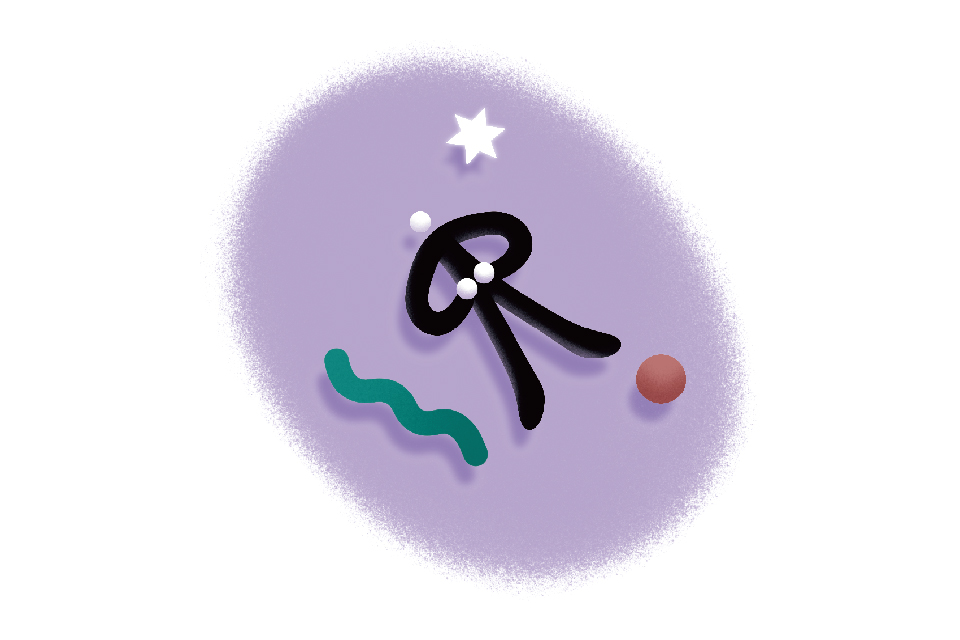
さまざまな感覚や特性をもつ人たち、そしてそれぞれの困難と向き合う人たちの声に耳を傾け、ともに語りなおすためにはどうしたらいいのだろうか。その術を模索し実践する、本・漫画・映画・現代アート、4分野の作品を手がかりに探ってみたい。
[文・編集] 白井暸、多田智美(MUESUM)、永江大(MUESUM)、鈴木瑠理子(MUESUM)
[イラスト] 飯尾あすか
REPORT|ともに笑い、怒り、語るために 「わたしの幻聴幻覚」プロジェクト

異なる他者の感覚に表現を通して向き合い、対話を生み出す。そんな実践が、愛媛・松山のNPO法人シアターネットワークえひめで行われている。精神障害のある利用者同士がそれぞれの抱える幻聴幻覚について聞き取りとスケッチを行い、カードや演劇の台本を制作し、制作物を用いたワークショップを通して共有するというものだ。2023年7月に開催された本プロジェクトの展覧会を振り返りながら、「聞く、語る、語りなおす」ことを考えてみたい。
[文・編集] 永江大(MUESUM)
[写真] 善家宏明
COLUMN|私たちは全然違うけれど、少しずつ似ているし、変わることができる
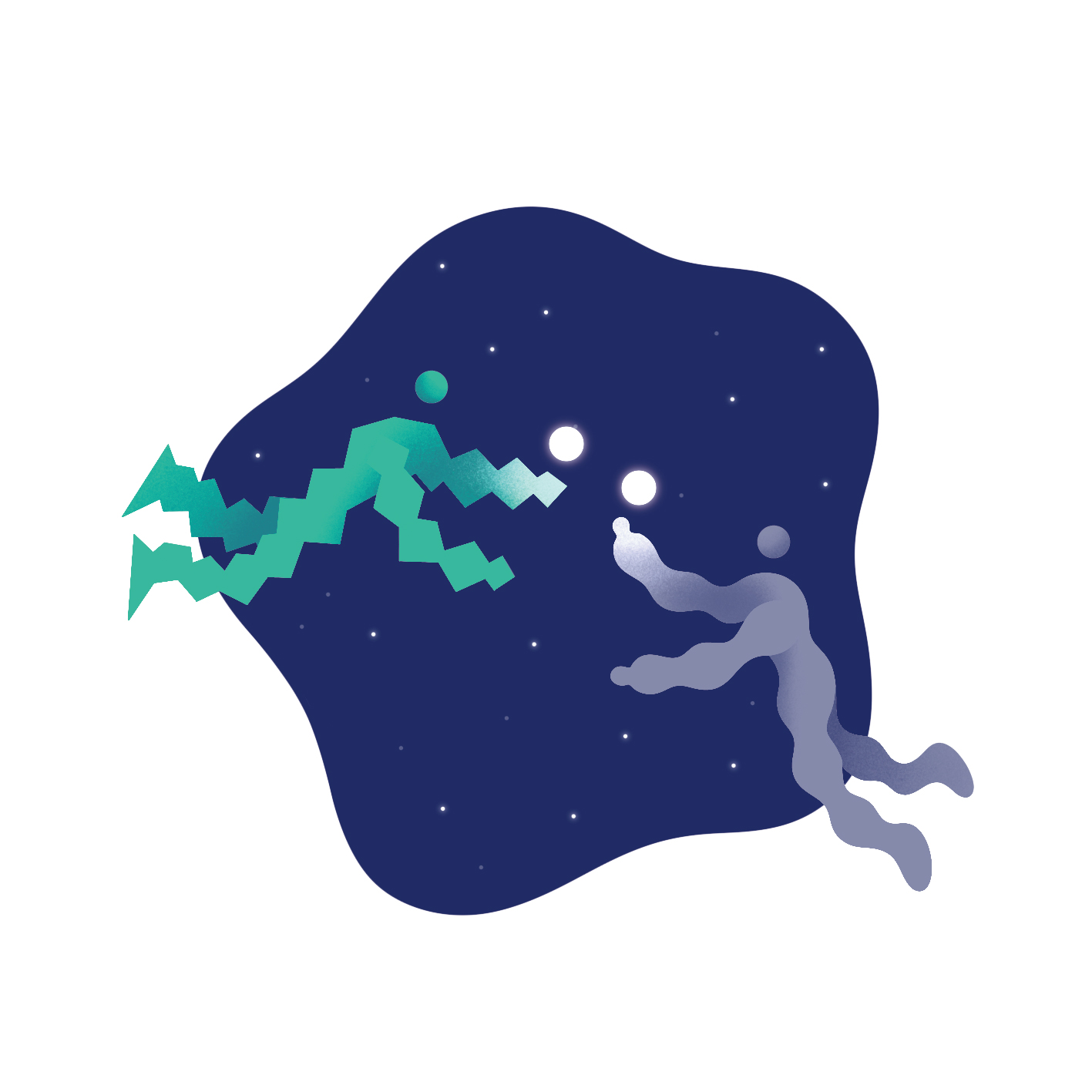
美術家・飯山由貴さんご自身の活動から、「語りなおすこと」をとらえるコラム。異なる感覚をもつ人を介して新たな言葉に触れ、学び直し、変化してゆく私たちの身ぶり。その積み重ねの先にあるものについて。
[文] 飯山由貴
[編集] 永江大(MUESUM)
[挿絵] 飯尾あすか
編集後記

幼い頃に親しんだ物語、歴史や事実を伝える証言、身のまわりの人との対話——誰しも、胸に響く「おはなし」と出合った経験があるのではないでしょうか。聞く/語るという営みは、相手と自分を確かめ合う手ざわりを実感させてくれます。揺らぐ自分を差し出し、相手を信じることから紡がれていく「おはなし」。だから、苦難を歩き、希望を見出すために、私たちのそばにあり続けるものなのだと感じました。
DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.15は、PDFでもご覧いただけます。
DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.15
発行元:日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS
編集:MUESUM(多田智美、永江大、鈴木瑠理子)+白井瞭
アートディレクション&デザインUMA/design farm(原田祐馬、岸木麻里子、大隅葉月)
校正:鴎来堂
印刷:シーズクリエイト







