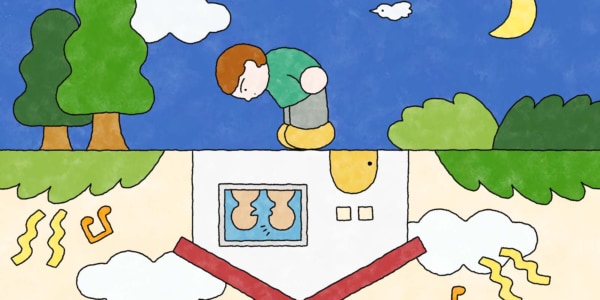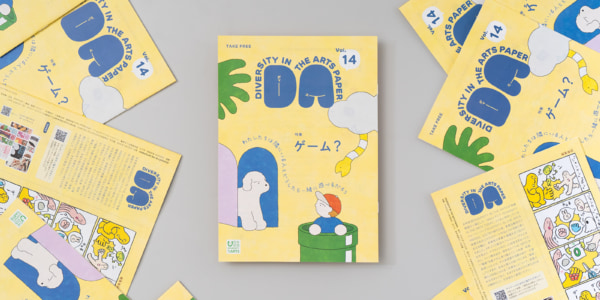ステートメント
特集:ゲーム? わたしたちは隣にいる人とどうしたら一緒に遊べるだろう
今、目まぐるしく変化する、ゲームの世界。あらゆるゲームのオンライン化やデバイスの革新、eスポーツの隆盛、プロゲーマーやストリーマー(動画配信者)の登場など、場所や時間の制約を越えて、さまざまな特性や感覚をもつ人たちが自然と一緒に遊べる環境・状況が生まれている。そんな「ゲーム」を通して、障害や表現のあり方を、本特集でとらえ直してみたい。そのヒントをうろうろと模索するなか出合ったのが、文化人類学者・早川 公(はやかわ こう)氏によるテキストの一節だ。
「ふつう」の枠組みに気づいて「ふつう」をつくりかえるにはどうしたらいいのでしょうか。-中略-「ゲーム」を通じてぼくたちは「障害」や「ふつう」の境界線をぼかして、新しい社会をつくれる可能性があるとぼくは思います。いわば、現実の社会をつくりかえていくために、ゲームがその「あいだ」となるんじゃないか
—ePARA「文化人類学者・早川公が語る!障害とゲームとSDGs〈連載1〉」より
他者との「あいだ」をつなぐゲームの世界に一歩足を踏み入れ、遊びながら、私たちの「ふつう」や「あたりまえ」をゆるがすための手がかりを探索すること。
まずは、そこからはじめてみよう。
もくじ
DIALOGUE|一緒に遊ぶ、からはじまること
NAOYA(ePARA所属アスリート) × なむ(ゲームさんぽ)

2023年10月、ePARA(イーパラ)とJR東日本スタートアップが主催となり、視覚情報に頼らないeスポーツ選手と一般参加者による格闘ゲームの交流会「心眼PARTY」が開催された。そこでストリートファイター6(以下、スト6)の対戦を行った全盲のプレイヤーNAOYAさんとゲームさんぽのなむさんが、当日のファイトを振り返りつつ、ゲームがつなぐ「あいだ」を語る本対談。ePARA代表の加藤大貴さんが立会人となり、アクセシビリティ、コミュニティとしてのあり方、他者の視点を知る実践など、いろんな方向へと広がりを見せた。
[文] 永江大(MUESUM)
[写真] 川瀬一絵
[編集] 多田智美(MUESUM)、永江大(MUESUM)、白井瞭
INSIGHT|ゲームがつなぐ「あいだ」って?

ゲームの世界と現実世界、2つの世界をテクノロジーと人がつないでいく。「一緒に遊ぶ、からはじまること――対談NAOYA(ePARA)×なむ(ゲームさんぽ)」にも登場した、ePARA・加藤大貴さん、ゲームさんぽ・なむさんとの会話を通して、ゲームがつなぐ「あいだ」の可能性を考えてみる。
[文・編集] 白井暸、多田智美(MUESUM)、永江大(MUESUM)、鈴木瑠理子(MUESUM)
[イラスト] hakowasa
REPORT|「AUDIO AR GAME MAKER」でオーディオゲームをつくって遊ぼう! ワークショップ体験記

2023年7月、AUDIO GAME CENTERによる新作ツール「AUDIO AR GAME MAKER」が発表となり、あわせてツールを用いたオーディオゲームづくりのワークショップが京都で開催された。ミュージアムエデュケーターの朴 鈴子(ぱく りょんじゃ)さんがその模様をレポートする。
[文] 朴鈴子
[写真] 衣笠名津美
[編集] 永江大(MUESUM)
COLUMN|ゲームを通して意味の網の目を揺さぶる
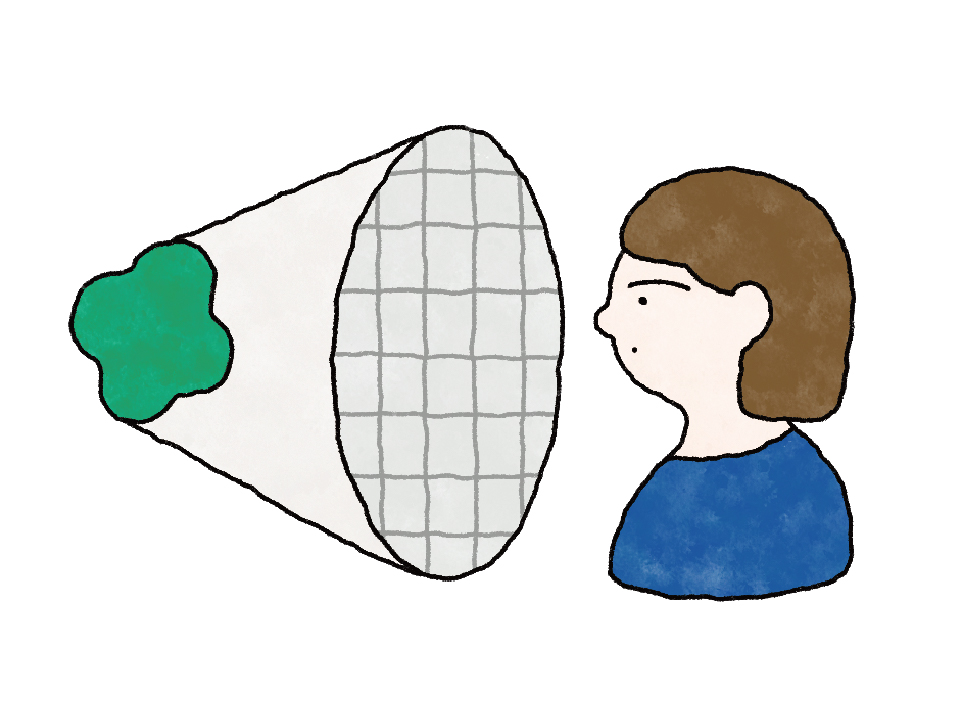
特集テーマ「ゲーム? わたしたちは隣にいる人とどうしたら一緒に遊べるだろう」を俯瞰する、文化人類学者・早川 公さんによるコラム。「障害」や「ふつう」の境界をぼかす営みに触れる。
[文] 早川 公
[編集] 多田智美(MUESUM)、永江大(MUESUM)、鈴木瑠理子(MUESUM)、白井暸
[挿絵] hakowasa
編集後記

ゲームは人々の「あいだ」をつなぐメディアになりうる。これは、今号の特集制作を通し、私たちが得た手応えです。「ゲーム(game)」の語源は、「楽しみ」「遊び」、そして「ともに楽しむ」。定められたルールにとらわれ、他者と関わり合う可能性を狭めるのではなく、やわらかくルールを更新し、ともに新たな視野をひらいていく。ゲームは、そんな実践を育む土壌と言えるのかもしれません。
DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.14は、PDFでもご覧いただけます。
DIVERSITY IN THE ARTS PAPER vol.14
発行元:日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS
編集:MUESUM(多田智美、永江大、鈴木瑠理子)+白井瞭
アートディレクション&デザインUMA/design farm(原田祐馬、岸木麻里子、大隅葉月)
校正:鴎来堂
印刷:シーズクリエイト