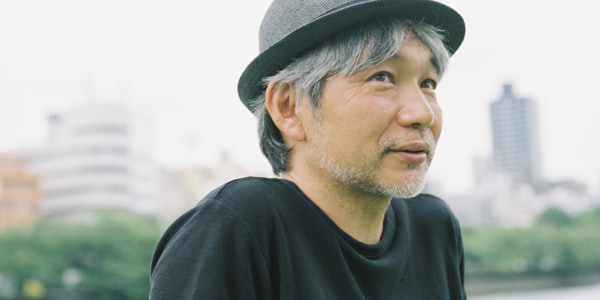絵本は子どもの成長に大切なツール
北イタリアの都市ミラノ。レオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》の壁画で知られる、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の裏通りには、見上げるほど大きな木の扉をもつ石造のアパートメントが並ぶ。その一角にある薄いオレンジ色の外壁をしたアパートメントの3階に、カルトゥージア出版(以下、カルトゥージア)のオフィスはある。
入り口で迎えてくれたのは、パトリツィア・ゼルビさん。カルトゥージアの創業社長で、編集長だ。壁の書棚に絵本や表彰盾がたくさん並んだ、淡い水色の応接室に私たちは通された。パトリツィアさんは、大きな楕円の机に山積みの絵本を手に取り、「すべての作品が、この部屋から生まれていったのよ」と語りはじめた。

パトリツィアさんが最初に紹介したのが、2009年に刊行された『タラリ タラレラ』(作:エマヌエラ・ブッソラーティ/邦訳は谷川俊太郎で2011年に集英社から刊行)。「この絵本は、日本や中国でも翻訳出版されているの」と言って、読み聞かせをしてくれた。彼女の口から聞こえてくるのは、イタリア語でなければ、英語でもない、架空の言語「ピリプ語」。この絵本には、ピリプ語を話すおさるのピリプ一家5人のある1日が描かれている。

パトリツィアさんが語る言葉に「意味」はない。だが、音感と絵がうまく重なり、ストーリーが想像できるのが楽しい。2010年にイタリアで著名な児童雑誌が表彰する「アンデルセン賞」のベストブックに選ばれ、発行部数7万部のベストセラーとなっている代表作だという。
「絵本は子どもの成長にとって基礎的で、大切なツール。子どもは本を通して、身のまわりのことを学び、世界について学んでいく。本は、触って、匂いを嗅いで、のぞき込んで、受け止めるもの。フィジカルな感覚から、思考も感情も刺激されていくの」
パトリツィアさんが絵本の出版をはじめたのは、大学生だった20歳の頃。カルトゥージアを創業する前に、仲間と出版社を立ち上げている。当時は、レオ・レオニなどが活躍した1970年代。まだ良質な児童書をつくる出版社が少なく、児童書出版社の立ち上げブームが起きていたという。活気あふれる時代のなか、レリーフの加工をした“触る絵本”をつくったり、読み聞かせのパフォーマンスをしたりもした。
そこで経験を積んだパトリツィアさんだったが、会社の方向性と自身の取り組みたい出版とのずれから、起業の決意を固めていく。そして1987年、28歳の若さで立ち上げたのがカルトゥージアだ。「自分ひとりでもできるって、示してやりたかったのよ」と、パトリツィアさんは振り返る。
「しかくいおはなし」に込めた、物語の力
パトリツィアさんは、「外国で成功した本の翻訳は簡単かもしれないけれど、ゼロからつくる創作絵本にこだわってきた」と編集方針を語る。現在、カルトゥージアの編集者は5人。創業37年で、刊行点数は約450冊。年平均12冊というのは、編集者の数からするとかなり少なく感じる。厳選された出版物のなかで、「カルトゥージアを体現する」と自負するのが、「しかくいおはなし」のシリーズだという。このシリーズは、判型が正方形で統一されていることから、そう命名されている。

絵本が取り上げるテーマは、どれも取り扱いが難しいデリケートな問題。生きづらさを抱える子どもたちが、生活のなかで直面する問題をテーマとし、「ケアすることを目的として出版している」という。
たとえば、小児がんをテーマに2010年につくった『しっぽをなくしたねこ』(企画:ガブリエレ・カラベッリ、サラ・フラスカ 作:エマヌエラ・ナーヴァ 絵:アンナリーザ・ベゲッリ/未邦訳)。
しっぽをなくしてしまった失意のねこが、しっぽを探しに宇宙を旅する。空気のない宇宙に旅立つにあたって猫がかぶるのが、かっこいいメッシュのマスク。このマスクは、子どもが放射線治療を受ける際に、顔面から頭を固定するメッシュ状に穴のあいた面がモデルとなっている。その面をつけることを嫌がり、全身麻酔をせざるを得なくなる子どもが少なくないことから、「お話で、子どもたちの気持ちをほぐせないか」と医療機関から制作の依頼を受けたのだという。

物語の最後は、ねこが勇敢さをトラから讃えられ、しっぽをもらう。この物語を読むと、メッシュの面が“怖いもの”から“あこがれの装備”に変わる子どもが多いそうだ。物語が目の前の現実のとらえ方をさりげなく教えてくれるのだ。

ディテールには明確な想定があるものの、解説されなければわからないほど物語が寓話化されているのも特徴だ。特定のテーマが下敷きにあることを強く打ち出すことはしない。現実から距離を置くことで、「子どもの心の深いところまで届く」とパトリツィアさんは物語の力を語る。
フォーカス・グループで本を共創
「デリケートなテーマであるほど、優れた書き手や画家の手を借りる必要がある」とパトリツィアさんは言う。物語のリアリティとクオリティを追求するために採り入れているのが、フォーカス・グループというユニークなチーム制。チームには、編集者、作家、画家に加え、当事者の子どもとその家族、心理学者、ソーシャルワーカーなどが加わり、一緒に物語をつくっていく。
「いろんな専門家とコラボレーションしてきた結果、こういう構成になりました。子どもの声を『聴く』ということを大事にしてきたんです。それも尋問みたいにでなく、気楽に、ね。小さくても、大きくても、子どもには話をちゃんと聞ける大人の存在が必要なんです」
制作の依頼は、社会福祉関係の財団などから持ちかけられることが多い。完成までに、1時間半〜2時間のディスカッションの場が4回ほど設けられる。
初回は、編集者のパトリツィアさんが、心理学者、ソーシャルワーカーなどの専門家とともに、子どもたちやその家族の経験の聞き取りを行い、レポートにまとめる。リラックスした雰囲気で、ピザやお菓子を食べたりしながら話を聞いていく。
次にテキストを担当する作家も聞き取りに参加する。作家は聞き役に徹し、取り上げるテーマに関するエッセンスが出揃ったところで、動物を主人公にする、昔話仕立てにするなど、ストーリーにまとめる方法を探っていく。
そして、テキスト案が出来上がると、協力してくれる学校に持って行き、子どもたちに読み聞かせを行う。その際、子どもたちにとってどんな場面が印象に残るかを知るために、文章や絵でフィードバックを得る。
最後に、画風の合う画家に参加を依頼する。過去の議論や子どもたちのフィードバックを共有し、完成に向けて進めていく。

このようなプロセスを経ることで、つくり手は「子どもの生活、経験を絵本に取り込むことができる」という。一方、フォーカス・グループに参加する子どもたちも、完成までプロジェクトの一員として創作に関わる。このプロセスによって、「子どもたちにとっても『自分の本』になり、ポジティブな種を心に残すことができる」とパトリツィアさんは語る。
フォーカス・グループの作業期間は、4ヵ月。「プロジェクトが間延びして、集中が切れないように」と、着手から半年後には完成させる。出来上がった本は、制作を依頼した団体が配布するだけではなく、本屋で市販する。ロングセラーになっている本も少なくないそうだ。
「しかくいおはなし」のシリーズは、自閉スペクトラム症の子どもが社会で生きる葛藤を題材とした物語や、大人でも子どもでもない思春期の子どもたちのアイデンティティの揺れを題材とした作品など、テーマはさまざま。だが、すべての作品が、生きるなかで傷ついた子どもたちが、物語のなかから希望を見出せる内容になっている。

「たとえ、テキストがない本でも、物語は絶対に必要」と、パトリツィアさんは強調する。近年は、「サイレントブック」と呼ばれるテキストのない絵本ジャンルを牽引し、多数の絵本を出版。ボローニャ・ブックフェアでコンテストも主催している。ほかにも、「国境なきおはなし」という各国の移民の昔話を多言語で紹介する蛇腹折のシリーズや、作家や画家が2人ずつ関わって創作する絵本シリーズなど、言語や形式にとらわれない柔軟で自由な本づくりを行っている。中核にある物語の表現に適したかたちや、制作プロセスを固定化せずに模索しているようだ。フォーカス・グループが生まれたのも、最初から構想があったのではなく、「子どもの声を聴くには?」を模索した結果だという。
いつの間にか、インタビューは休憩を挟み約5時間に及んでいた。窓からのぞく空はほの暗くなっている。さて、ここで聞いた話を、どう深め、生かしていくか、私たちの実践がここからはじまる。