『father』から7年を経て
半月舎で金川晋吾さんと細馬宏通さんのトークを開催したのは、実ははじめてのことではない。2016年夏にも、『father』の刊行記念として対談が行われた。企画・司会を担ったのは、金川さんの旧知で彦根在住の、現在は滋賀県立大学環境科学部で准教授を務める川井操さんだ。当時、同大人間文化学部教授だった細馬さんに川井さんが声をかけたことがきっかけで実現したのが最初である。それから約7年の時を経て、同じお三方の顔ぶれと、再び店でお目にかかれるとは思わなかった。感慨深くなり、『father』トーク時のわたし自身のFacebookを見返すと、こんな感想を書いて投稿していた。
「個人的には自分の考えや感覚に正直であることはひとつの才能とか技術がいるなというのが日々の所感でして、そこにどういう形で踏みとどまるかということが昨夜のひとつのテーマだったように思います。(中略)『人間のわからない心』という言葉が写真集のテーマとして帯に綴られていましたが、『わからない』ままでおくということもひとつの答えとしてごろんとある、そんな作品集のように思えました」
このとき同時に印象に残ったのは、「失踪を繰り返す父」という穏やかならぬテーマとは裏腹に、あまり深刻さを感じさせない金川さんの素朴な佇まいだった。いわば“問題”を抱える父親を作品の題材としながら、たとえば「さらけだす」というような言葉も似合わない、あったことを自分が感じたサイズ感で語る率直さ。そこに起きるギャップが大きな魅力のように思えた。


「いなくなる」ということ
新著の『いなくなっていない父』では、『father』が話題となったことで、失踪癖で知られるようになってしまったお父さんと金川さんご自身との関わりについて——ごく幼少の頃の記憶から、お父さんを撮影するようになった経緯を経て、『father』刊行とその後に至るまでが、散文のかたちで綴られている。文字通り、父親は「いなくなっていない」。実際、金川さんがお父さんの写真を撮るきっかけとなった2008年の失踪、そして『father』にも記録された2009年の失踪の後は、お父さんは行方をくらませてはいないという。
では、「いなくなる」とはそもそもどういうことなのか?今回のトークでも最初の話題となったこのテーマについて、細馬さんはこう投げかけた。「『いなくなる』って、境目が難しいですよね。『失踪』ってかなりきついっていうか、昔は『蒸発』という言葉もあったでしょう。『蒸発』って、『いなくなる』ということの最北端みたいなところから、『留守にする』ぐらいの簡単なところまで(振り幅がある)」。すると、金川さんは「うちでは『蒸発』って言い方をしていましたね。『失踪』よりもニュアンス的に、含みをもった情緒があって。今は気体になってるけど、また液体に戻るみたいな」とイメージを語り、会場の笑いを誘った。
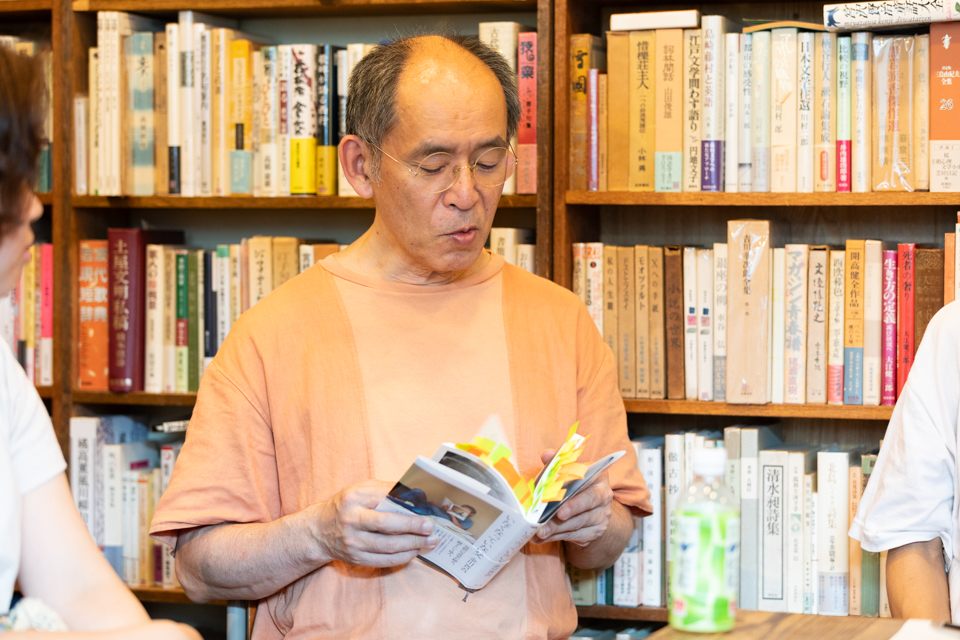
しかし、お父さんの蒸発を「家出ぐらいのこと」ととらえつつも、「もしかしたらもう帰ってこないかもしれない」「自殺とかも、万が一……?」という思いはあった。そして一番やっかいだったのは、家に戻ってきたときだとも。たしかに、家庭内に漂う、どんな言葉を発すればいいのかわからないような気まずさは想像に難くない。だが、細馬さんはそんな状況を描写する金川さんの書き方を「ユーモアがある」と言い、惹きつけられた箇所を随所で読み上げた。たとえば、こんな一節。
「戻って来てから数日は、父はやつれた雰囲気を全身から発することで、私や母や兄に有無を言わさないようにしているように見えた。」
お父さん自身の居心地の悪さや、それを感じ取る家族が居合わす空気感が思い浮かぶようだ。しかも、いたたまれない場面であるはずなのに、どこかおかしみを帯びて感じられてしまう。また、お父さんが家に再び馴染んでいくときの目印もあるのだという。そうした時期の金川さんのまなざしが、以下のような描写に表れている。
「(前略)それは一緒にテレビを見ているときに、父がテレビ番組について何かコメントというか解説のようなものを語るということだった。解説といってもネットニュースに載っているような雑学程度のものであったり、あるいは何の根拠もない主観的な予想、たとえばサッカーの試合でPKになったときに、『これはなんか外す気がする』と神妙な顔で語るとか、そういう他愛のないことなのだが、そういうことを口にできるかどうかがひとつの分水嶺になっていたと思う。」
細馬さんは「ワンクッションある気がする」と、気まずさを振り返る際の、金川さん独特のとらえ方について指摘した。たしかに、こうした体験をしたのは金川さん自身だが、それを自ら俯瞰(ふかん)するような視座がにじみ出ているように思う。金川さんはゆっくりと考えながら、言葉をつむいだ。「そういうことがあったときに、誰かに言おうっていう、その宛先が僕のなかにある。こういうふうに作品(写真や本)にするっていう(意識と、その)宛先があるから、もうひとつ距離が取れているような気はしました」

「日記」という表現の手法
トーク後半は、『いなくなっていない父』の章立てに沿いながら、『father』刊行後、お父さんと金川さんのドキュメンタリー番組がNHKで制作されることになった際の話題へ。取材や撮影の過程が語られていった。そして、細馬さんがまた幾度か文章を読み上げる声を聞くなかで、ふと金川さんは「今、自分が書いた文を読んでもらうっていう経験をしてみて、これはとても妙なことだなと思いました。他人が読むと、もうひとつ距離があるというか。書いたものと自分って、違うんだなっていうか、重なっていない部分がある」と実感をこぼした。
金川さんは、微細で率直な語り口の「日記」という形式で文章を綴っている。そうしたかたちで書きはじめたのは、『father』制作時の2008〜2009年、失踪し、人生もままならなくなった父の生活を立て直すために通っていた時期、記録としてつけるようになった日記がきっかけだった。父について、また自分自身が感じていることについてを記していきたい。そうして書いてみると、それまで自分が文章を書けるとは思っていなかったが、奇を衒(てら)わず「あったこと」を書く行為に手応えを感じるとともに、次第に表現の手法としても着目するようになった。以降、その興味は、参加者がそれぞれに日記を持ち寄り音読する「日記を読む会」を主宰したり、日記のワークショップなどを行ったりするほどに深まっていく。
「日記って、基本的には人に見せないだろうし、そのつもりで書きますよね。でも、そういう個人的なものを人にひらいて、シェアしたら面白いんじゃないかと考えたんです。書き残されたものを誰かが読む可能性は必ず生じるわけだし、そもそも書くということは、誰か他者に向けられている。日記の場合も、それを誰に見せるつもりがなくても、未来の自分という他者に向けて書いていると言えると思うんです」と金川さんは言う。
それを受けて細馬さんは、「金川さんの日記へのスタンスは、『ここがつかえてるんだよね』と人に話すことでちょっと楽になる、そういう構え方なのかもしれない」と応じ、「その上で、ウケを狙うようなおもしろエピソードとしてではなく、もしかしたら自分のプライバシーに関わることや、ちょっとひらきすぎかなと思うようなことも含めて、正直に書くバランスが大事なのかもしれないね」と続けた。

自分自身をひらく営み
終了時間が迫るなか、最後は参加者との質疑応答の時間に。ある学生の方からは、「私的な出来事や自分自身の反応を、日記を通して公表していくことは、金川さんにとってどういう意味をもつのか。また、写真と日記というふたつの表現をどう両立させているのか」と質問があった。
金川さんは「私的なことをあえて『公表』するというよりは、前提として、(表現する上で)自分のことを語るべきだという感覚がまず僕にはあって。何かを発するからには、『自分はこう感じている』と言いたいし、そうでしか語れない」と口にした。
そして、表現手法についてはこう語った。「写真っていうのは、そこにあるものを写すという手法なので、僕がいろいろなことを考えたとしても、写真には写ってこないんですよね。もちろん、そういうものを入れなくてもよければそれでいいんですけど、僕は『こんなことがあった、そしてこんなことを思った』というのを入れたい。最近思うのは、写真だけだと、人はそこに何か“いい物語”をつい見出したくなるところがある。たとえば親父の写真だけを見たら、『内面に深い悩みをもった何者か』ととらえちゃうと思うんですよね。だから、その背後にある具体的なものごとを書くことで、気を散らせるというか。そのために言葉を使っているのかもしれません」

それは、世間に対して自分自身の実体験を赤裸々に訴えかけるというよりも、他者と自分との関係性、そこに渦巻くものにどう向き合ったかを自ら振り返り、伝える方法なのかもしれない。トークを締めくくるとき、金川さんは「“わたくしごと”は話しにくいことかもしれませんが、僕はもっと話せたほうがいいと思っています。『私的なことだから自分の内側にとどめておかないと』って、思わなくていいようになるといいなあと。何が私的なこととされるのか、おおっぴらに話すべきではないとされるのか。そう問うこと自体が、公的な、いわば政治的な営みだと考えています」とも話していた。
生きづらさ、と言うほどでないとしても、「しっくりこない」「何か居心地が悪い」と感じたり、とらえどころのない気持ちを抱くことは誰にでもあると思う。そんな自分をひらき、率直な態度で向き合うことで見つかるものがある。それは自分に正直に、幸せに生きたいと願う気持ちのひとつの指針になるような気がした。トークイベント中も、金川さんはずっと、ゆっくりひとつずつ、時には行きつ戻りつしながら、とらえどころのなさを言い当てる言葉を探していた。今回はその様子がとても印象に残っている。










