アートの秘密は脳にある
人間には言葉を話すという生得的な能力があります。
アートとはそうした言語能力の一つの表現が洗練されたものであると考えられます。ですから、小説や短歌はもちろんアートですし、そのテキストを読めば朗読、振りを付ければ演劇、抑揚を付けると歌というアートになる。さらに言葉を取り去って楽器で演奏しても音楽になります。言葉に縛られることなく、はじめから視覚的な世界を表現する絵画や彫刻もアートですし、生活に根差した道具や建築なども、すべてアートになり得ます。そして、このアートを生み出せるのは人間だけで、その秘密は人間の脳にあるのです。

アートを語る上で、障害のあるなしは─何をもって障害とするのかという定義すら─関係ないと思います。なぜなら、人間であることになんら変わりがないからです。たとえ「障害者が描いたその絵は偶然の産物では?」と言う人がいたとしても、あえて偶然性の入る手法を選ぶことも含め、そこには必ず作り手の意図があるものです。
私はゴッホの絵が大好きです。彼は当時二人の医師から「複合妄想を伴う急性の精神錯乱」や「相当長い間隔をおいたてんかん発作」と診断されましたが、ゴッホは絵筆を握ると気分がとても落ち着いたそうです。誰しも心の状態は一定ではありません。ゴッホは非常に強烈な個性を持った人であり、そうした「個」がなければ、あれほど真に迫る作品の数々は生まれなかったでしょう。
絵筆を握ったときに、我を忘れて集中したり、創造のモードに入ったりすることがあるものです。ゴッホも弟のテオに宛てた手紙の中で、「自分の病気に一番いいのは絵を描くことだ」と、書いています。そもそも異常な興奮状態や抑制状態では、絵筆を握ることもままならないでしょう。
アートに障害のある、なしは関係ない

論文で報告された、あるイギリス人女性の例を紹介しましょう。彼女は若くして認知症を発症しましたが、50歳を越えてから初めて絵を描き始めました。ほどなくして、風景画の才能が開花します。日常生活では脱抑制状態といって、突然泣き出したり、叫び出したりすることがありました。側頭葉の損傷により、前頭葉に対して本来あった抑制が効かなくなったわけですが、それが芸術的才能を引き出すことにもなったと考えられます。
認知症だからといって単純な作業を繰り返させたりするのではなく、塗り絵や書道、作句など、より知的な活動を積極的に活用することが大切だと私は考えます。ゴッホや彼女の例からもわかるように、知的な活動によって、脳が人間らしい「創作モード」に切り変わりうるからです。

障害のあるなしは、目に見える見かけの姿に過ぎません。最も肝心なのは脳の中の状態であり、内的な心のあり方なのです。訳知り顔で使われる「身体性」という用語にも私は疑問を感じます。たとえ身体が全く動かなくとも、沈思黙考し、周りのうかがい知ることができない非常に創造的なプロセスが進んでいるかもしれません。スポーツ選手の高い身体能力は、瞬時に判断を下すという頭脳なしには引き出されないでしょう。
認知症や脳の損傷というと、脳機能が「低下した」「なくなった」という負の側面だけで捉えがちですが、逆にプラスに働くケースも実際にあるわけです。決して外見にとらわれてはいけませんね。
ベートーヴェンは聴覚を失ってさらに才能が開花した

ベートーヴェンは若くしてボンの街からウィーンに出て、気鋭のピアニストを目指しましたが、まさにこれからというときに耳が聞こえなくなっていきました。しかしベートーヴェンは、その絶望の淵にあって、たとえ聴覚を失おうとも作曲なら続けられ、そしてさらに深められるということに気づきます。実際、それまで全く試みられたことのないような数々の名曲を新たに生み出したのでした。もし聴覚を失わなければ、あれほどの傑作を世に残さなかったかもしれないのです。
聴覚を完全に失った後にベートーヴェンが作曲した『交響曲第9番』などを指して、「障害者が作ったアート」と言う人はいないでしょう。それではなぜ彼は耳が聞こえないのに、優れた曲が作れたのでしょうか。これはベートーヴェンに限らず、すべての創作に通じる奥義なのですが、真の芸術作品は「頭の中で作る」ものだからです。
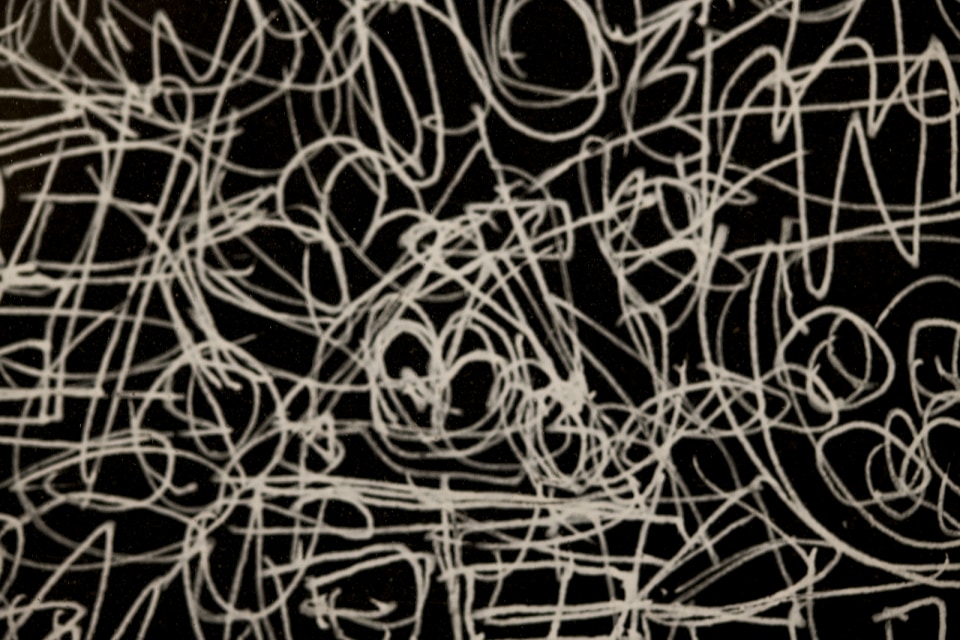
ベートーヴェンは幼少時から音楽のトレーニングを受けていましたから、他の音楽家と同様に、頭の中で複数の音を同時に鳴らすことができたわけです。それはちょうど、優れたシェフが実際に料理をする前に、頭の中で素材を組合わせて、美味しい料理の味を的確に思い描けるのと同じことです。ベートーヴェンの脳裏には、ほかの音楽家では聞きとれない音までが鳴り響いていたことでしょう。だからこそ、誰も聞いたことがないほど美しいハーモニーの曲が作れたのです。むしろ実際に聞こえる音を超えた、理想的で純粋な音楽の美を追求できたのかもしれませんね。
要するに、人間の脳こそがすべてのアートを生み出してきたのです。多くの人は障害のある人の作品を目にすると、ハンデキャップという表面的なラベルを付けがちですが、いったんアートを生み出す脳の中に分け入ったら、見かけの問題など消え去ってしまうでしょう。そこは深い教養、洞察、そして発見に支えられた世界なのですから。
美しさとは、芸術とはなんなのかという問い

面白いことに、作品を鑑賞する側には、芸術家と同等の力量を持つことが要求されませんし、それでも作品の良し悪しがある程度までわかるものです。本格的な楽器演奏や合唱、そして作曲の経験がない人でも、『第九』を聞いて楽しむことができますし、感動や勇気を味わうこともできるでしょう。
もちろん、芸術の本質を深く知る人は、素晴らしい作品に接することでさらに奥深い体験が得られることと思います。そして、文明と縁のない生き方をしている人でも、もっと言えば千年後の人類であっても、『第九』の力強いメッセージを受け取れるのではないでしょうか。つまり、優れた作品には、すべての人間に等しく通じる「普遍性」があるわけです。
日本画家の千住博先生は、「美とは何か」という難しい問いかけに対して、「生きることそのもの」とお答えになっています。私たちは美しい作品から、「生きたいと前向きになる力」をもらうのです。そこに芸術の普遍性があるのだと合点がいきました。
芸術家が作品を作り、人々が鑑賞することで、互いに想像力で補いながら通じ合っているのです。創作家が鑑賞者のことを一顧だにせず、独善的で高踏的な作品に固執するとしたら、やはり芸術家たる想像力が足らないと思います。つまり芸術は、双方が同じ側に立って初めて成立するものであり、「共に生き、互いにわかり合いましょう」という強力なメッセージなのです
千住先生のおっしゃる「生きること」とはなんでしょうか。それは「喜び」や「楽しさ」といった直接的な感覚かもしれないですし、「驚き」や「面白さ」といった知性の表れかもしれません。人は優れた芸術作品に接すると、自然と心を揺さぶられるものです。それが生きる力になるのだと思います。

(C)Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung 撮影:酒井邦嘉
先日、私は古代エジプトの作品、特にアマルナ美術の粋を目の当たりにして、その緻密さ、リアリズム、そして普遍的な美に目覚めました。数千年経っても、人間は全く変わらぬ美意識を持ち続けているのです。脳科学で考えれば、同じ脳を持っているから当たり前とも言えるのですが、それもまた不思議なことではありませんか。
芸術とは共生の精神

今や、自分と自国を優先する風潮が新型コロナの影響で一層強まっています。「自分がコロナにかからなければ何をしてもいい」「自国にワクチンが優先的に確保できればそれでいい」という状況になりがちです。そうした分断は、芸術の目指す共存の方向とは明らかに真逆です。むしろ、このような時代だからこそ、芸術こそが生きていく上で本当に必要なものなのだ、と明らかになったとも言えましょう。
芸術という考え方はまさに共生の精神であり、多様性をありのままに認めるということです。それは、互いに対するリスペクトがあって初めて成立します。地域・社会・文化・宗教・価値観などがどれほど違っていても、結局は同じ人間ではありませんか。
言語の問題も同じです。表面的には英語と日本語はだいぶ違うように思えるかもしれませんが、どちらも手話と同じように赤ちゃんが自然と覚えられる自然言語です。
真のグローバル化とは、誰もが同じ言葉を話すということではなく、相手の言葉にリスペクトを持ち、できるだけ相手の言葉で話そうとすることです。そのためにも、アートを通してエンパシー(共感力)を培うことが、本当に大切なのだと思います。

撮影協力 :社会福祉法人友愛学園 成人部、Kanzan gallery、江戸東京博物館、Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung




