
アトリエで制作する松浦繁さん。
左手から彫り出す“地球”の一片
宮城県仙台市在住の松浦繁さんは、木彫の作家だ。19歳で脳内出血にかかり、病院のリハビリで木彫と出会った。以後、後遺症が残った現在も、左手のみで制作活動を続けている。
一時退院中に訪れたカルチャーセンターで出合い、現在も通っている造形教室の先生が、片手で彫る方法を教えてくれた。作業は鋸や電動ノミなどの道具を使い、万力という工具で材木を押さえながら掘り進めていく。
松浦さんの作品が目を惹く理由のひとつは、その色にある。原色は使わずに、水分を多めに含んだ絵の具を混ぜながら、下地の上へ色を重ねていく。筆を使うときもあれば、何度も何度も指でなでるように塗るときもある。表面が彫った跡で凹凸としているので、一度に色がべったりと張り付くことはなく、疎らなレイヤーが豊かで軽い色彩を生んでいる。

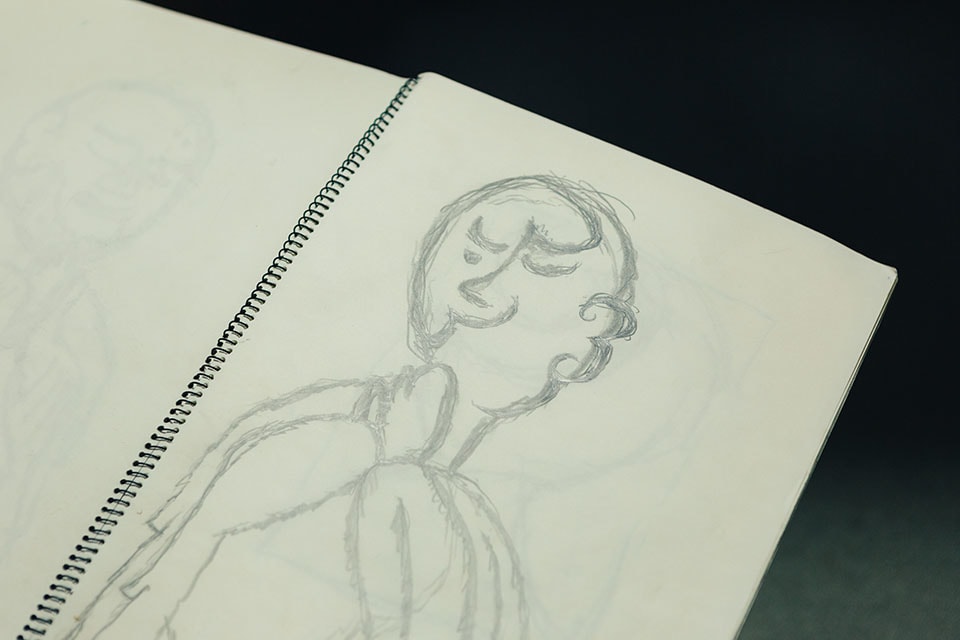
松浦さんの円空さんのスケッチ。
木彫をはじめたころは、花や鳥など、具体的なモチーフを写実的に模刻していたが、今は抽象的な荒彫りへ興味が向かっているという。
「なにかをそっくりそのままつくることを続けていても、いずれ飽きてしまって、木彫自体を辞めてしまっていたかもしれません。抽象には『暇』があると思います。病気になってから、自分は『暇』を持ったと思い、抽象的な作品が合っているのではないかと考えたんです」と松浦さん。その移行期の作品で、具象と抽象の交じった《鳩》は、7割ほど制作を進めたが、引越しの際にどこかへいってしまったそうで、今となっては見ることができないのが残念だ。

「手術を受けた25歳あたりから、制作のテーマは一貫して『地球』です。ちょうど、湾岸戦争がはじまって、オウムの事件が起こって、阪神・淡路大震災もあった。たまたまかもしれませんが、破壊に関することが続いた頃で、『地球』ってなんだろうなぁって考えていたんです」

身体の自由が効かないからこそ、なにかをつくりたい
現在制作している《希望》は、テレビで観たモアイ像を気に入って、その造形をヒントに、明るさが天へ向かっていくようなイメージが表現されている。
「新しい作品に取り掛かる際には、まずスケッチをたくさん描きます。《希望》は、残材でひとまわり小さい習作をつくり、半年ほど前から実作に手をつけはじめました」。ひとつの作品の完成には、だいたい10ヶ月ほどを要するのだそうだ。

作品を観るのも好きで、これまでに直島(香川県)など、遠くの土地にも家族と一緒に美術鑑賞の旅へ出かけたという。好きな芸術家は、岡本太郎とアンソニー・カロ。特に岡本の作品《太陽の塔》には惚れ込んで、それをモチーフにした過去作もある。その出会いは衝撃的で、大阪から琵琶湖へ向かう風景の中で偶然目にし、思わず走っていた車を止めてもらうようにお願いしたとか。どこかで見たかたちを、自身の木彫の手法で、新たに構築し直すプロセスが多いようだ。


生涯に推定12万体の仏像を彫ったことで有名な、江戸時代の仏師である「円空さんが好き」だとも教えてくださった松浦さん。普通なら使わないような材木を捨てずに活かし仏を生み続けた「円空さん」のように、松浦さんも、最初のイメージに沿う造形にならなかった場合でも、そこで終わらせることなく、直したり、継ぎ足したりしながら新しい存在を与える。「身体の自由が効かないからこそ、なにかをつくりたいと思う」と語る松浦さんの仕事は、淡々と、「地球」の一片を彫り出している。













