当事者研究以前に始まった、当事者たちの運動。
子どもの話の前に、私が取り組んでいる当事者研究についてお話ししますね。「当事者」とは、障害のある人のことですが、当事者研究は何もないところから生まれたわけではなく、それに先立つ取り組みがあって、しかしそれでは足りなかったので生まれたという歴史があります。
当事者研究に影響を与えた取り組みはたくさんありますが、大きくは2つに分けられます。ひとつは当事者運動といわれるものです。社会は、身体の特徴あるいは経験において平均的なマジョリティの体質の人向けにできているので、いろんなサポートが得られますが、マイノリティの体質の人は建物や道具のデザイン、価値観、社会規範という社会を構成するあらゆる側面が自分とそぐわない傾向がある。そうなると、一般の社会の中で他の人たちのようには暮らせないので、行く場所が隔離された施設か家庭の中にしかなくなってしまいます。両親亡きあと、社会の中で暮らしていくためにはどうしたらいいのか。当事者運動は、こうした背景と医学モデル的考えに対する批判から生まれました。つまり、障害のある人は、ノーマルとされているマジョリティへと訓練して自分を近づけなくてはいけない。変わるべきはマイノリティだと捉えているのが医学モデルの考え方です。そうではなく、社会の側が、社会を構成するあらゆるデザインをマイノリティにも有効なものに変えることが必要なんじゃないかと。
たとえば、身体障害など、比較的目に見えやすいマイノリティ性のある人たちは、社会に飛び込みさえすれば黙っていても身体がマイノリティ性を表現します。身体自体がアートであり、表現する媒体なんですよね。そういう人たちは、根性で社会に居続けさえすれば、モーゼ(の海割り)のように社会が徐々に変わっていくわけです。そういう彼らが勇気を持って当事者運動をしてきたという歴史があると同時に、その流れに置いていかれた当事者もいました。二分するわけではなくグラデーションなのですが、そうした人たちの多くは、黙っていたら表現が伝わらない、見えづらい障害のある人たちでした。

目には見えにくい自分の障害について、自分で研究すること。
深刻さを過小評価されやすいというマイノリティ性とは、どんなものがあるでしょうか。聴覚障害もそうですし、発達障害、PTSD、LGBTもそうかもしれません。そして、見えづらい障害というのは、当事者自身からも見えづらいんです。なぜかわからないけれど、周りと同じようにできない。その理由が不明な場合、努力が足りない、意思が弱いんじゃないかというふうに、自分の人格を責め始める。そういう苦しさから当事者研究という、見えないものを見える化する取り組みが始まりました。当事者運動の思想は受け継ぎながらも、身体からマイノリティ性がほとばしり出ていない当事者がまず表現活動をしないといけない。自分のことも相手のことも、お互いに同じ部分と違う部分を知らなければと。
なぜ「研究」という言葉を使うかというと、正解を知らないという前提に立つことを重視しているからです。かつては、専門家が正解を知っていて、正解を知らない当事者は専門家に従う、という医学モデルが正しいとされていた時代がありました。当事者運動を経て、当事者こそが正解を知っている専門家だと立場を反転させましたが、どちらも少し違う。当事者研究というのは、専門家も当事者も知らない前提から始まります。自分のこともよく知らないし、相手のこともよく知らない。当事者研究ではこれを前向きな無力さと呼んでいます。無力さを自覚したからこそ、知らない者同士膝を付き合わせて研究をしよう、と対等な形でテーブルにつくことができる。もう知っているから後は変えるだけというのが運動ですが、変える前には知らなきゃいけない。変える手前に留まるのが当事者研究の大事なポイントです。つまり、当事者運動から批判的に継承されたものが、当事者研究のひとつの側面です。
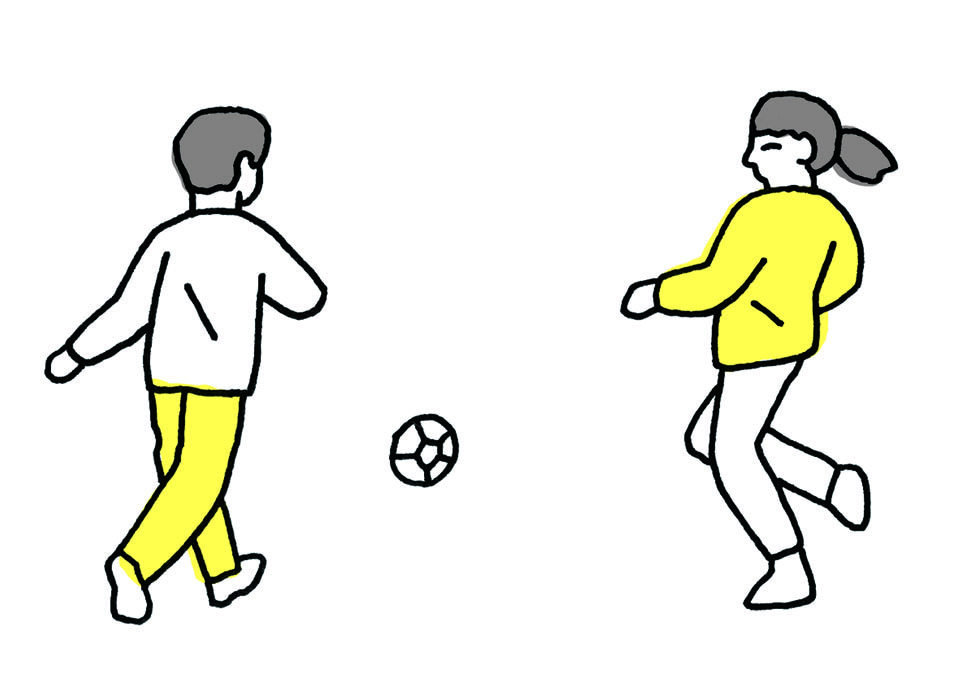
トラウマと向き合ってきた、依存症自助グループから学ぶこと。
2つ目に当事者研究が非常に重要なところを受け継いでいるのが、薬物依存症とアルコール依存症の自助グループの長い歴史です。こちらも、医療は何もできないと匙を投げたものでした。依存症の人は、多くの場合小さい頃に虐待を受けている、あるいは戦争という国家からの虐待を受けていることが多い。つまり、暴力の被害者である可能性が高いということが最近になって知られてきました。この暴力あるいはトラウマという側面に真っ正面から向き合ってきたのが、自助グループの歴史です。被害者性は加害者性とニアリーイコール(ほとんど等しい)な部分がある。つまり、暴力に被害で巻き込まれているという現象にいるという上では同じなんですよね。これを当事者活動の中にもたらしたのが、依存症自助グループの歴史的に重要な意義です。
虐待や暴力を受けると人はまず、身近な人に依存してはいけないということを学習します。そうすると、物質、自分、カリスマなどへの依存が加速していきます。また、トラウマ記憶が頭の中に入ってくるので、自分が自分である根拠となる過去の記憶全般を遮断せざるを得なくなる。そのために覚醒度を上げるか下げるか、ワーカホリックになる。これは依存症あるあるなんです。専門家は、この6つの特徴をなんとか治そうとしてきたけれど、大事なのは2つでした。虐待は変えられない事実ですが、そこから派生する、身近な人に依存できなくなるということ、過去を遮断することが介入ポイントであると依存症自助グループが見抜いたんですね。

当事者運動と依存症自助グループの要素をミックスして生まれた、当事者研究。
どちらかというと、未来に向かってどんどん突き進んでいく部分が強かった当事者運動に対して、自助グループは力点を過去に置いています。過去を振り返らない前向きさというのは非常に脆弱(ぜいじゃく)なところがあって、本当の前向きというのは後ろを向けることです。これは当事者運動も軽視してきたところでした。なので、当事者研究は、依存症自助グループが提案する回復プログラム「12ステップ」に象徴される、身近な人にもう一度頼れるということと、過去の棚卸しをしていくことを大事にしています。誠実に過去を振り返って、それを仲間と分かち合うという未来の展望を自ずから生み出す。トラウマがあると、それが起きた瞬間の前後で時間軸に断層が生じて、物語が途絶えてしまうんです。それをもう一度1本のストーリーとして再構築する必要があるのですが、順序がとても重要で、現在、過去、未来の順とよく言われています。まずは、現在に安全な日常と住まい、人間関係を構築する。それまでは過去を無理して振り返っちゃいけない。でないと、フラッシュバックした瞬間、過去にワープしてしまうんですね。その人を引き止めてくれるのは現在の地場、まさに手を繋げる仲間がいるというリアリティが身体に染み込んで初めて過去を振り返れるようになります。
当事者たちの語りを発信していくことが、社会を動かすことにつながる。
当事者という言葉よりも研究という言葉に力点を置く理由としては、無知の知と公開性という特徴があります。当事者運動に比べて、トラウマなどが非常にセンシティブなので自助グループのミーティングは、基本的には閉ざされた中で行われてきました。ただ、一歩外に出れば、社会の無理解にさらされる。そうすると、傷ついて再び依存してしまうという事例が後を絶ちませんでした。多くのマイノリティは社会基盤を変えないと救われない。当事者たちの語りを何らかの加工をして発信していかなければ社会は動かないんですね。自分たちのミーティングで作り上げてきた表現を公開するところまでいって初めて、当事者研究と呼べるということで、自助グループと当事者研究の違いは公開性の有無であるとよく言われます。学会発表をしたり、世界に発信しなければ、研究とは呼べません。人類全体に公開して、人の目にさらして批評も受けながら練り上げられていくのが研究ですから。
また、当事者研究は医療のセラピーのひとつとして誤解されやすいのですが、医療の限界からスタートした取り組みなので、医療の一環ではありません。目的は治すことではなくて、知ること。だから、治らなくてもいいという人しか参加しないほうがいい。当事者研究をする人も、ほかの研究者と同じように、生きやすくなることを目的に研究しているわけではありません。そこに謎があるから、不思議だから知りたい。知ることで、結果的に生きやすくなるというものなんです。
障害を持つ子どもだった自分を救ってくれたもの。
私には脳性麻痺という障害がありますが、私がまず救われたのは、当事者運動でした。恩人である先輩方が切り開いて継承してきたもの、そこで蓄積されてきた表現や実践によって私は生かされたという感覚があります。私が子どもの頃は、とにかく身体をノーマルに近づけるという医学モデルが信じられていたので、親の愛情もそちらに流されていくわけです。子どものことを思えば思うほどリハビリをさせなきゃいけない、それがこの子にとっては幸せなんだという知識の中で育てられました。当時は、ヨーロッパを中心とした専門家たちの間で、「脳性麻痺は治る」と言われていましたが、オイルショック後に、どの治療法も効果がないということが証明されました。これが、先ほどの無知の知のスタートですね。医療が正式に敗北を認めたことが、私たちにとってはものすごい恵みだった。私の身体が悪いのではなく、社会環境が問題なんだと180度視点が変わった。ようやく生きていけると思いました。
また当事者運動が、「医学モデルである優生思想(優秀な能力を持つ者の遺伝子を保護すべきとする考え)に毒されている親も被害者であり、真の加害者は社会全体だ」と謳ったことは大きかったですね。親はただ養育責任を課せられるという重圧の中で、愛情と無意識に内在する差別意識が渾然一体となってスティグマ(ネガティブなレッテル)が濃縮してしまう。だからこそ、日本の障害者グループの先駆けである「青い芝の会」の横塚晃一氏が、「泣いても詫びてでも親の愛情を蹴っ飛ばさなきゃいけない」と言ったことで、親から注がれている愛情を否定していいんだと思うことができました。彼は「愛と正義を否定する」とも残しています。愛も正義も少数派を排除した多数派の論理で作動してしまっているので、よきものとされるんですよね。だからこそ立ち向かうことが難しいけれど、まずそこを疑ってかかれと。そうした言葉に救われて、私もようやく息ができるようになりました。
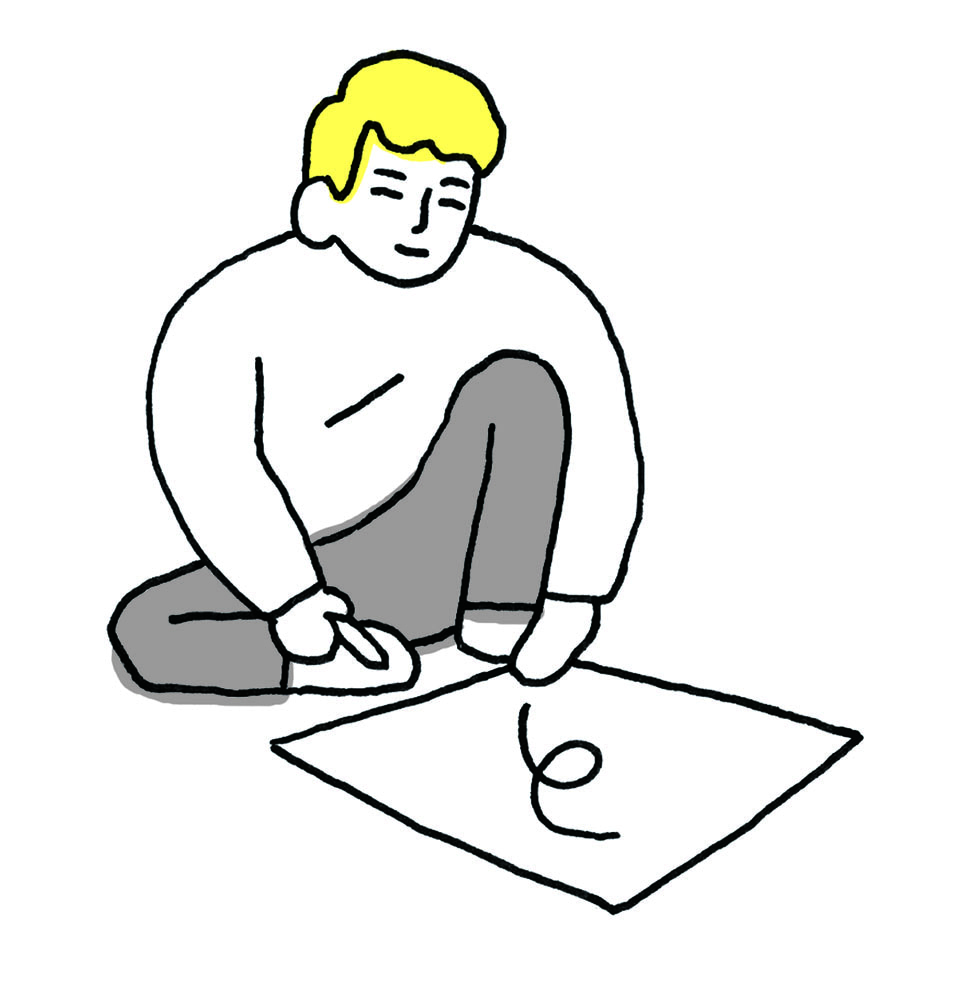
親以外の縦のコミュニティとの出合いが、生きる力になる。
私の場合は、父親が学生運動をしていたのですが、仕事は市役所の職員として障害者福祉課で障害のある人の対応をしていたんですね。80年代になると、社会運動が盛んになってきて、異議申立ての窓口対応をしていた父は、平日は過激な障害のある運動家に頭を下げながら、休日になると彼らと中学生の私を引き合わせてくれました。僕はここで出会うわけです。言わば、反社会的な悪い先輩たちに(笑)。
当事者のコミュニティに受け継がれている思想や系譜は、横軸だけではなく、縦軸もあるんです。当事者同士のコミュニティにも縦軸があって、上の先輩たちの背中を見ながら受け継がれるもので、ようやく息が吸えるようになることがある。ここで重要なのが、フラットな関係ではないというところです。彼らが語っていた言葉や実践は、オルタナティブな縦軸として流れ込んできました。自分よりも重度の障害のある人たちが生き生きと生活している。家も出てアパートを借りて、施設にも入っていないし、デートしたり子どもが生まれたり人生を謳歌しているらしい。子ども心に詳細不明ながらも、親以外の人が介助をして生活が成り立っているという先輩たちの背中以上のエビデンスはありません。オルタナティブなストーリー、ナラティブ(自分について物語ること)を先輩の障害者から教わって、こんな状況定義があるんだと思えた。自分の人生をこんなふうに語り直していいのか、というナラティブ資源みたいなものがたくさん流通していることが大切なんです。家庭の中の密室にいた頃はナラティブの資源を手にすることができなかったので、自分の表現し難い不安を言語化できませんでした。
人は、理念や理想を掲げて初めて、生きられるところがあります。一方で、等身大の当事者の語りというのはもっと苦しいものです。つまり、縦軸の系譜で受け継がれてきた当事者のナラティブと、それには含まれない生々しい今を生きる当事者たちの横軸のナラティブ、その両方があって初めて全貌が見える。今は、健常者は縦軸があるけど、当事者には横軸しかないという風潮が若干出ていますよね。縦軸は悪いもので横軸は美しい平等なものだと、縦軸は見逃されてきました。でも、やっぱり当事者には当事者の獣道があって、先人たちの歩んできた足跡がその道を照らしてくれているんです。照らすものがあって初めて希望というものが湧く。縦横のナラティブをどんなふうに後世に受け継いで、拡張していくかがとても重要なんですね。
残念ながらナラティブは自分の中からは生まれず、共同性の中からしか出てこない。縦横揃って初めて生まれるので、そこをつないでおくことが切実に求められる。そういう場所を作るサポートをすることも、周囲ができることかもしれません。
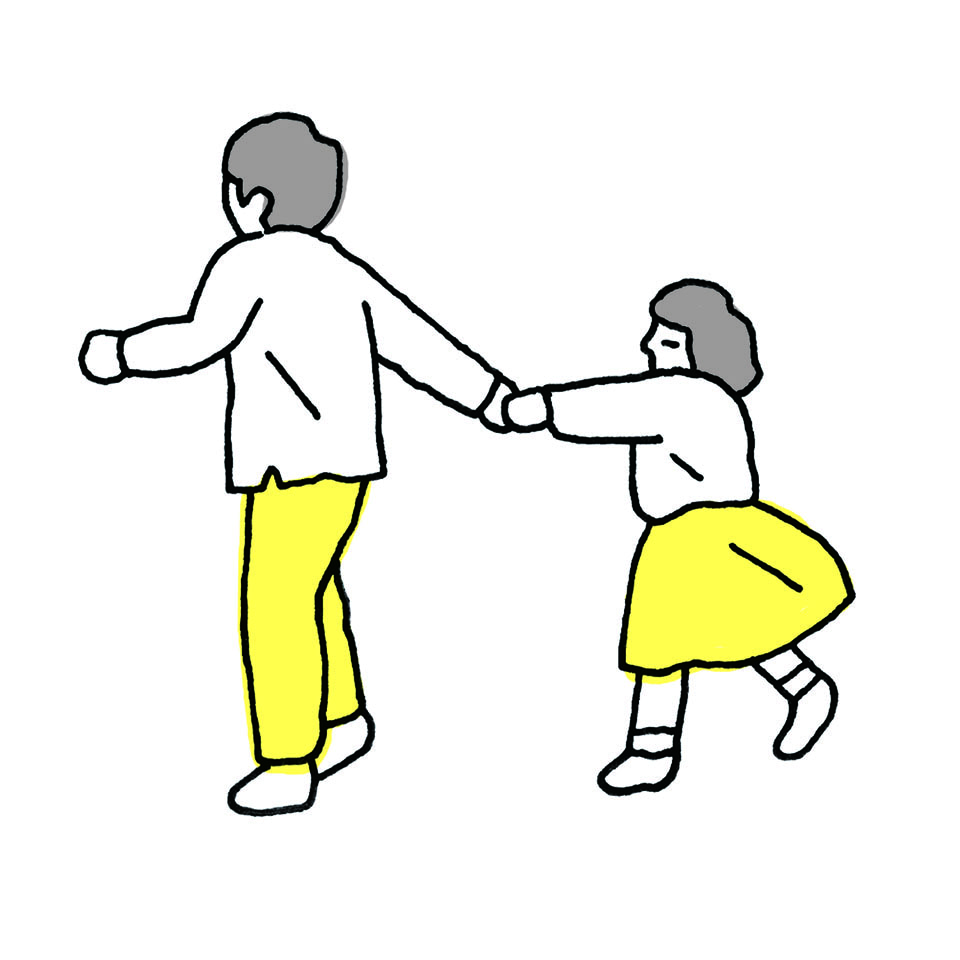
依存先を増やしていくために、私たちができることってなんだろう?
幼少期のネガティブさは、依存先が限られていたということから生まれる部分が大きいんです。生きていくためには24時間誰かの介助が必要になるわけですが、それが親だけに独占されている状況だと、親のご機嫌をとらなくてはいけなくなり、依存が加速してしまう。なぜならその人に見捨てられたり、死んでしまったら生きていく術がないからです。一人暮らしをしたとき、先輩が「30人は介助者がいないと駄目だ」と言いました。その理由は、人間は定期的に不機嫌になったり暴力的になったりするので、1人の人が暴力的になったときに残り29人いれば、その人との関係を解消できると。腕っぷしの強さでは圧倒的に弱い私たちが、弱いままでも対等に尊厳ある暮らしを保つためには数で勝負するということを先輩から学びました。人数比というのは決定的なんです。障害のある当事者が家庭でも施設でもなく地域にこだわった理由のひとつは、人数比です。依存先がたくさんあるということを実現する可能性のある場所は、地域しかない。地域もまだまだなんですけど、家庭や施設では人数比的に生存基盤として自分の意思が尊重される暮らしが成立するということは、あり得ないんですね。
では一人ひとりが依存先を増やすためにできることのひとつに、インフラの面の整備があります。愛というものは排他的で、独占性を生むので生存基盤に直結してはいけません。生存以上のところで豊かなものであってほしいですが、生存基盤が愛だけでは怖いんです。極端に言えば、依存先を社会化、市場化する必要があります。独占や寡占というのは市場の失敗ですよね。そういう意味で、すべての人のニーズが無視されないためにはどうしたらいいのか、というのは市場経済学が考えてきたことなんです。これを引き続き、しっかり考えていかないといけない。これは障害者の問題だけではありません。誰にとっても依存先がたくさんあることは大切なこと。そのために財政はどうしなければいけないのか頭の中で整理して、投票行動につなげていくことが重要です。自分が依存先のひとつになれるような振る舞いを一人ひとりが考えることも、必要になってくるかもしれません。
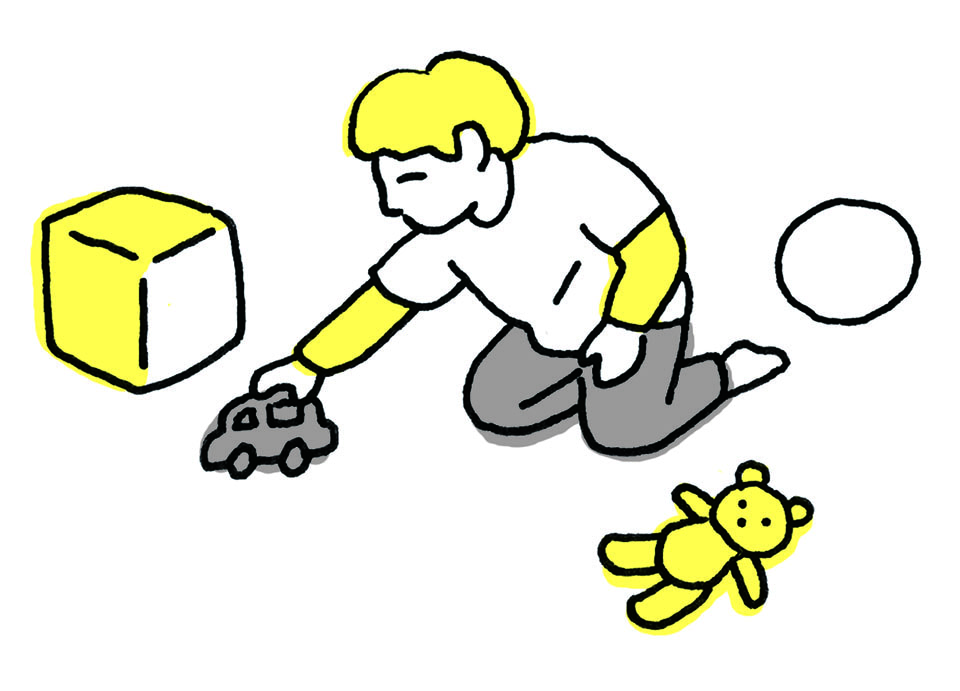
差別意識を社会から減らしていくために。
下部構造にある依存先を増やしていくことと同時に、上部構造、意識の面でスティグマを減らすことも周りの人ができることのひとつです。さっきのナラティブと深く関わるのがスティグマ(※差別や偏見)ですね。障害者やLGBTなどの集団をグループ化するカテゴリーに対して、ネガティブなレッテルを貼る社会現象のことをスティグマと呼びます。これは、インフルエンザのようなもので、生まれたての赤ちゃんはスティグマを持たないので、後から学習するんですね。まずは、人の差別的な言動を見て感染する。2段階目としてカテゴリーの典型的なタイプを頭の中で作り上げてしまう。3段階目として、偏見が出てきて、そのイメージに対してネガティブなレッテルを貼る。ここまではまだ潜伏期間。人にウイルスをまき散らす4段階目を、差別と呼びます。それは、行動として表出したスティグマであり、人に影響を与えるもの。スティグマ現象というのはその属性を持っている人を殺しかねないものなので、今は特定の属性に対するスティグマをどうやったら減らせるのかがWHOをはじめとする専門機関にとって最優先課題のひとつとなっています。
差別は行動として表れたら罰することができるのですが、法律には内心の自由という制約条件があるので、潜伏期間には介入できません。法律は1/4だけに対応できるので、3/4はどうするかというと、広い意味での教育のようなものが必要になります。では、どういう教育カリキュラムが必要になるのかを世界中の人たちが研究しているのですが、シンプルな結論に到達しつつあります。それが、当事者のナラティブを聞くということ。ただし、身近にいる家族や支援者、専門家は、当事者のナラティブをずっと聞いてきていますよね。でも、統計データによると、近親者がスティグマの発生源になっていることが多い。要するに、よく知らない人たちは差別意識を持っていないんです。家族や支援者のように利害関係が生じている人が憎しみや恨みを持ったりするからこそ、スティグマが発生して世の中に広がっていく。どうやらナラティブはシンプルじゃないらしいということも徐々にわかってきました。私たちが当事者研究でまさに研究しているのが、どのようなナラティブが、どのような出合い方をすればスティグマを減らせるのか。もう一歩踏み込んだ人類分析をする必要性があります。
正直なナラティブに触れられる場としての、芸術作品。
先行研究としてナラティブを3つに分類した人がいます。ひとつ目は社会に対する異議申立てタイプのナラティブ。当事者運動的な語りですよね。2つ目は、上から目線の教育的な語り。3つ目は、自分の身に起きたことを正直に語る自伝的ナラティブ。どれが一番周囲の人のスティグマを減らしたのかというと、自伝的ナラティブなんです。正直に自分の経験を語ることが、本人にとっての自助グループのような意味での回復につながるだけでなく、それを慎重に開示していくことがスティグマを減らす効果も発揮するかもしれないという仮説を立てて今リサーチをしているところです。
自伝的ナラティブは、本や映画などの芸術作品が勝負していることと、すごく似ていると思います。芸術作品も、当事者研究と同じように、個人の安全性を配慮した上で社会を動かすために少しだけリスクを取りながら表現しているのでしょうから。








