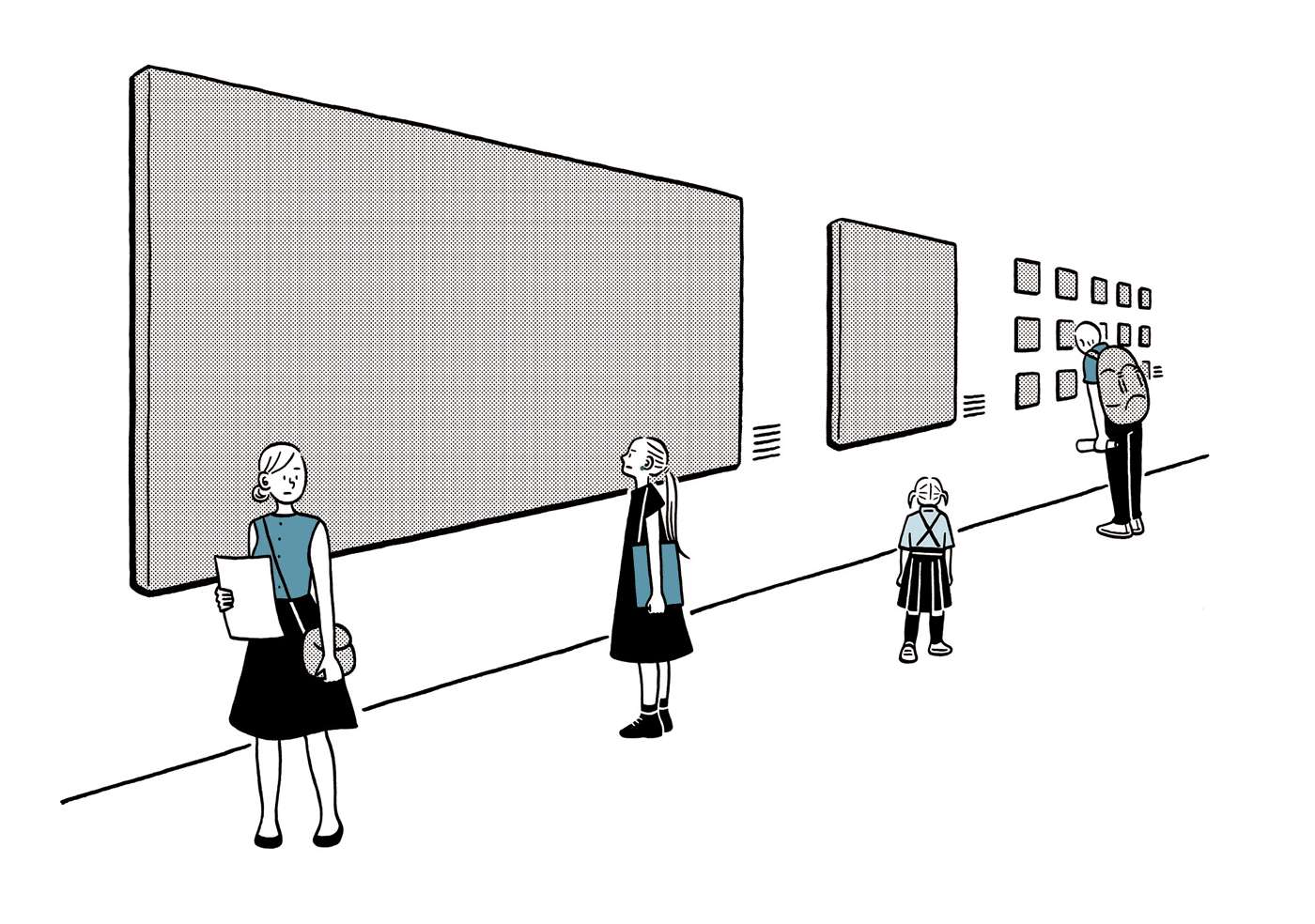画家・デュビュッフェの葛藤と憧れ
アール・ブリュット
「アール・ブリュット」はフランス人の画家、ジャン・デュビュッフェが考えた造語です。「ブリュット」はフランス語で「加工していない」「ありのままの」という意味。ワインや木材といった飲食物や素材に使われる言葉で、芸術でいうと「アートに加工を施していない」というニュアンスになります。デュビュッフェがこの言葉を提唱した1945年は第二次世界大戦が終わり、あらゆる価値観が変わった重要な年でした。
戦時中の1943年、当時42歳だったデュビュッフェは、長らく家業にしていたワイン製造の仕事をやめ、芸術家として生きていく決意をしました。終戦を迎え、それまで近代美術で扱われてこなかった精神病患者、受刑者、子ども、民俗芸術や交霊術によるアフリカやオセアニアの人たちの作品など、非西洋美術史に関する資料や作品を集めようと旅に出ます。このデュビュッフェが収集した資料や作品を含むコレクションにつけた名前が「アール・ブリュット」だったのです。彼はこれらをまとめて見せる場所「アール・ブリュットの家」と、アール・ブリュット協会をつくりました。この協会には、デュビュッフェの呼びかけにより、人類学者のクロード・レヴィ=ストロースや芸術家のアンドレ・ブルトンなど著名な文化人が多数参加しています。
彼はこのコレクションを厳しく管理しました。パリの美術館でアール・ブリュットの展覧会をした際、作品を見た人に「こういう作家がいるけれど、私たちもアール・ブリュットと呼びたい」と言われると、「これは私のコレクションだからその言葉は使ってほしくない」と答えたそうです。
またデュビュッフェは、自身も身を置いている近現代美術に嫌気がさしていました。キャリア志向で模倣が横行する近現代美術に対し、アール・ブリュット作家の「つくること」と「生きること」が切り離せない切実さや生きる姿勢に、憧れを抱いていたのではないかと思います。本人は「アール・ブリュットに影響を受けていない」とも言っていますが、自分のためだけの屋外彫刻作品《ヴィラ・ファルバラ》に挑戦しています。こうした制作への姿勢からアール・ブリュットから影響を受けていたことが伺えます。
アウトサイダー・アート
1972年、このアール・ブリュットをイギリスの美術批評家、ロジャー・カーディナルが「アウトサイダー・アート」と英語に訳し、紹介しました。この「アウトサイダー」という言葉にまつわるそれまでの動きをみていくと、アメリカの社会学者であるハワード・S.ベッカーがアーティストやミュージシャンの、社会から逸脱した行動を論じた「アウトサイダーズ」(1963年)という論文を発表しています。このなかでベッカーは「生まれながらのアウトサイダーはいない。社会の規範があるから逸脱者が存在する」と論じています。また1956年にはイギリス人の作家、コリン・ウィルソンの小説『アウトサイダー』がヒットしました。さらにこの60〜70年代というのはカウンターカルチャーの全盛期。宗教的な伝統や社会のルールが厳しく、セクシャルマイノリティへの偏見も多かった時代です。社会のなかで鬱屈していたものが爆発し、学生運動やウッドストックにつながっていきました。「アウトサイダー」は、文学や映画、小説、美術などの世界から見ると、規範を壊すヒーローだったのです。
芸術の革命はいつもその外側から
プリミティヴィズム
次に、アール・ブリュットやアウトサイダー・アートが生まれる前のヨーロッパにはどのような言葉があったのでしょうか。近現代美術のなかで生まれた言葉に「プリミティヴィズム」があります。19世紀、植民地主義によりアフリカやオセアニア地域の文化がヨーロッパに伝わりました。ピカソやブラックら、ヨーロッパの芸術家たちは、植民地の人びとがつくる仮面や彫刻に影響を受け、キュビスムという動向につながります。この現象を「プリミティヴィズム」と呼んでいます。日本語にすると「原始志向」でしょうか。ただ「プリミティヴィズム」と言ったのは西洋の研究者でした。西洋から見るとアフリカ社会は原始であり未開の地であるといった一方的な視点が含まれる言葉です。
ナイーヴ・アート
さらにこのころ庶民階級出身の独学による作品が「ナイーヴ・アート」と言われました。日本語では「素朴派」と訳されますが、欧米では「ナイーヴ」とは、世間知らずな、単純な(稚拙な)といったニュアンスを含むマイナスの意味で使われることが多いのです。西洋美術史においても、ルネッサンス以降の遠近法など近代美術の規範から見て「美術の世間知らずな」という視点が入っています。「ナイーヴ・アート」は税関吏として働いていたアンリ・ルソーをピカソたちが発見したことに始まっていますが、ピカソら芸術家たちは上から下を見るような目で彼らを見ていたわけではありません。衝撃を受けて真似をしたり、影響を受けて新たな表現を生み出したりと、そこには敬意がありました。
オートマティスム
「オートマティスム」という言葉にもアーティストがかかわっています。1920年代、フランスの詩人、アンドレ・ブルトンを中心とする芸術家たちのシュルレアリスムという運動から生まれた言葉です。彼らは狂気や夢想、無意識の世界に対する憧れを抱き制作をしていました。オートマティスム(自動記述)はそのなかの一つで、できるだけ無意識の状態に近づけて文や絵をかく方法でした。美術の革命の核となるものは、美術の外にあるというのは、いつの時代も美術史の宿命でしょう。
アール・イレギュリエ
こうした世界や今昔のさまざまな言葉で語られる文献を整理するために生まれたのが「アール・イレギュリエ」です。フランスの国立図書館が文献を分類する際につけたカテゴリー名ですが、「イレギュリエ」はフランス語で、レギュラー(規範)に対する「反規範」を指します。作家、ジュール・ヴァレスの1965年に刊行された本から抜粋された言葉で、「アウトサイダー」と同じく“かっこいい”意味で使われています。ヴァレスは本のなかで、社会規範をつくるブルジョワたちに反する芸術家、詩人、活動家などを「イレギュリエ」と呼んでいました。
新大陸のアイデンティティ
フォーク・アート/セルフトート・アート
ここまでヨーロッパを中心に紹介してきましたが、一方で、西洋に端を発する近現代美術に対し、新大陸・アメリカでは自国のアイデンティティについて考えられてきました。
そこでアメリカ独自の言葉として登場するのが「フォーク・アート」や「セルフトート・アート」です。これらはアメリカ大陸の開拓時代、アフリカから連行された人たちや南米からの移民、ブルーワーカーと呼ばれた労働者、また農村地帯の人たちによる作品が含まれます。ニューヨークにはアメリカン フォーク・アートミュージアムもあり、これはスイスにあるアール・ブリュットコレクションに匹敵する美術館です。
自由の国・アメリカではフロンティア精神が根底にあり、旧大陸(ヨーロッパ)の文化の「歴史」に対して自分たちのアイデンティティを正当化する意味でも、セルフトート(独学)は好まれた言葉だと思います。個々人が開拓すれば誰でも上っていける夢のある社会。そのスピリットから「セルフトート・アート」という言葉が好まれるのではないでしょうか。
福祉と哲学から生まれた日本の言葉
エイブル・アート
最後に日本独自の言葉を紹介します。フランスにとっての狂気や無意識、アメリカにとってのフォーク(民芸)のように、日本にとっては福祉が大きな特徴として挙げられるでしょう。ほかの国を見ると、シュルレアリスムとアール・ブリュットは、精神医療との連携はありますが、医療は「medical」で「well-fare(福祉)」ではありません。「福祉」という概念すらない国もあります。
日本の福祉分野の動きから生まれた言葉の一つに「エイブル・アート」があります。日本語で「可能性の芸術」です。エイブル・アートは1995年、障害者の方々が社会の中で生きやすくなるようにと、日本障害者芸術文化協会と財団法人たんぽぽの家により提唱されました。
日本障害者芸術文化協会の初代会長が嶋本昭三という具体芸術運動の作家だったことは注目したい部分です。障害のある人たちの作品に対する嶋本昭三の眼差しには、ナイーヴ・アートを見つけたピカソ、アール・ブリュットを見るデュビュッフェに共通するものがあるのではないかと思います。別の世界へ目を向けることは、自身の規範をくつがえすことでもある。こうした芸術家たちには、わからないことを知ろうとし、つくり上げた自分の規範をあえて危険にさらすような共通点が見られます。
限界芸術
明治以降、近代の「アート」の波が押し寄せ、日本国内からも近現代美術が生まれていきました。日本社会が西洋を追いかけすぎた時代、「インターナショナルアート」からこぼれたものや入らないものをとり上げ論じたのが「限界芸術」です。哲学者の鶴見俊輔が提唱しました。職人が歌う民謡、盆踊り、漫才、民芸、落書きなど生活に根付いた文化に対して呼んだ言葉です。
言葉には、そこに生きる人びとの時代の精神が隠れている
文化や芸術が語られるなかで、翻訳により言葉の本来の意味や意図が変わることがあります。たとえ、同じ言語を使う場合でも、私たちは聞いたことや考えたことを翻訳して相手に伝えます。その際、個人や集団の帰属する時代や地域、社会の認識基盤に基づいて解釈して翻訳します。デュビュッフェがあれだけ大切に守った「アール・ブリュット」という言葉も、現在では広く使われるようになりました。特に日本では、学問や美術史の言葉としてではなく、障害者の芸術表現とともに、ある種親近感を伴った形で広まっています。エスカレータ、バンドエイド、ホッチキスなど商標だったものが一般名称化することがありますが、デュビュッフェも亡くなり、日本でアール・ブリュットは一般名称となりつつあります。このようにある言葉が他の時代や他の地域に流入し、その意味が変わったりすることは長い歴史のなかではよくあることではあります。
そもそもデュビュッフェが嫌っていた教養人のアート、つまり「近現代美術」は万国共通の「ユニバーサル」な美術史があるという考えのもとに成り立っています。万国共通の美術史とは、地政学的に強いパワーを持つ西洋が確立した美術史です。この西洋社会主体の「インターナショナルアート」の枠組みに含まれないものとして、西洋社会ではアール・ブリュットやアウトサイダー・アートという言葉を生み出しました。
では、非西洋圏の日本はどうでしょうか。日本美術史が西洋の「近現代美術史」に並走するとき、日本画や工芸などは万国共通の「ユニバーサル」な歴史の尺度では必ずしも測ることはできないかもしれません。そもそも「ユニバーサル」な尺度など存在しないのですから。アフリカ諸国でも、現在の作家が作る作品で、現代美術にあてはまらない民俗芸術なのか、民族芸術、霊媒芸術なのか、個性芸術なのか、工芸なのか、職人技なのか問われるような作家もいます。言い換えれば、それぞれの地域から見た芸術の歴史は、万国共通の美術史とは異なる視点であって当然なのです。
言葉は地域や集団、時代によって好みもあり、意味も変化していく。言葉が生まれる背景には必ず理由があり、文化、歴史、社会、思考といったそこに生きる人びとの時代の精神が隠れているのです。「ユニバーサル」「インターナショナル」と歴史を一つの方向に淘汰していくのではなく、あらゆる視点があることを知り、その違いを検証することは、翻訳できないニュアンスをコミュニケーションすることができる一つの手段であると同時に、自分たちの社会が持つ認識基盤や先入観を改めて確認することにもなります。